『トイ・ストーリー 謎の恐竜ワールド』は、ボニーの想像力から始まり、忘れ去られたおもちゃたちの世界で繰り広げられる短編。
トリクシーとレプティラスの出会いが物語を動かし、遊びと存在意義をめぐる気づきを描いているの。
相関図①|ボニーの想像力とトリクシーの悩み
冒頭からいきなり全力で駆け抜けてくるのがボニーという女の子。彼女は『トイ・ストーリー』シリーズにおけるアンディからおもちゃを受け継いだ子供で、まだ幼いのに想像力の爆発力がすごいの。
大人が「恐竜」として作ったフィギュアも、ボニーにかかれば角があるから「トナカイ」になったり、ゴブリンの妖精になったりと、自由自在。大人がどう名付けたかなんて関係なく、子供の遊びの中では意味づけがガラリと変わっていくものだと思うの。
ママも子供のころは人形やぬいぐるみでごっこ遊びをしたけれど、ここまで突拍子もない設定変更はできなかった気がするわ。だからこそボニーの遊び方を見ていると、子供の発想の飛躍にただ感心するばかりになるの。
この世界には暗黙のルールがあるのね。子供の前ではおもちゃは命あるかのように勝手には動かない。そこがあるから成立しているのが『トイ・ストーリー』の世界観で、これが崩れたらホラーになってしまうわね(笑)。

でも、おもちゃたちは子供のことをよく観察している。ボニーが「恐竜が逃げた~」と走り去ると、トリクシーは「今の聞いた?」と問いかけ、レックスは「心配だよね」と応じる。恐竜が逃げたことを心配しているようでもあり、ボニーの突拍子もないテンションを見て「あの子大丈夫なのかな」と言っているようにも聞こえるのがユーモラスで、観ている側もくすっと笑ってしまうの。
戻ってきたボニーはまた違う遊びを始める。今度はエンジェルキティは「猫サウルス」という設定で登場。エンジェルキティはかわいい見た目なのに、時折「広い心で世界を受け入れなさい」といった達観した言葉を発する存在。
ボニーの想像力を見たバズが「科学を超えた神秘だな」と評していたけれど、それは決して大げさではないと感じるわ。遊びが展開していく速さにも驚かされる。まだ始まって1分50秒しか経っていないのに、すでに濃いドラマが詰め込まれているように思えるの。
短編だからこそ一気に畳みかける展開にする必要があるのかもしれないけれど、観ている側にとっては「え、もうここまで?」と置いていかれるくらいのこさを感じるの。
そんな冒頭の流れの中で、今回の主役であるトリクシーが悩みを打ち明ける。トリクシーは青いトリケラトプスのおもちゃで、普段は明るくておしゃべり好きなキャラクターとして知られているけれど、めずらしく弱さを見せるの。
「まだ恐竜として遊んでもらったことがない」というのが彼女の悩み。自分が恐竜の形をしているのに、一度もそのまま恐竜として扱ってもらえていない。それは彼女にとって存在意義が揺らぐほどの大問題に感じられるのかもしれないと思うの。
子供のおもちゃにとって「どう扱ってもらえるか」が存在の全て。だからこそトリクシーの悩みは深刻そう。そんなトリクシーもボニーのお出かけ選抜メンバーには選ばれる。
でも、与えられた役割は「トナカイ」見たいね(笑)。悩んでいるトリクシーにかけられたエンジェルキティの言葉は「広い心で世界を受け入れなさい」(笑)。
ボニーと母親が向かった先は友達のメイソンの家。メイソンは専用の遊び部屋やゲーム部屋を持っているお金持ちの子のようで、画面に映る姿はビデオゲームに熱中している少年。
でも、その姿はただのわがままな子供という印象ではなく、素直さを残しているように見えるの。
レックスが「こんな小さな手じゃゲームはできない」とつぶやくと、またもやエンジェルキティが「できないという概念は自らを縛る足かせです」と言い放つ。確かに、子供って「できない」と言われても何とか工夫して遊びを成り立たせることあるわよね。
相関②|忘れ去られたおもちゃたちとレプティラスの登場
ボニーに放り出されてから、いよいよ「子供の目」が消えた場所でのおもちゃたちの世界が描かれていくの。
映画の原題は「Toy Story That Time Forgot」。直訳すれば「忘れ去られた時」という感じ。描かれているのは「忘れ去られたおもちゃたち」の姿。
子供に遊んでもらえなくなり、ただ置きざりにされたおもちゃが大勢いるって感じね。遊んでもらえないままでは、確かに、自分が何者なのかを見失ってしまうのかもしれないと感じるわ。
メイソンの部屋にずらりと並ぶ恐竜ベースの戦士たちは、とにかく数が多い。残念なことにメイソン自身はほとんど手を触れていないようなの。
コンプリートされたセットには、遊びを作り出す余地が意外と少ないのかも。だから彼の関心はすでにゲームに移ってしまっているように見える。
子供の心を掴めないまま放置された彼らは、やがて自分たちだけの世界を築き始める。そこに君臨するのが「賢者クレリック」と呼ばれる存在。
名前こそ賢者だけど、彼が考えていることは支配と独裁。遊んでもらえない寂しさや孤独が歪んで、支配の方向に突き進んでしまったのだと思うの。
遊びを知らない存在が集まると、そこには戦いしか残らないみたいね。バズやトリクシーのように「遊びを演じる」ことを知っているおもちゃとは対照的に、彼らは真剣に戦うことしか考えていない。
その姿は子供の世界と大人の世界の対比のようにも感じられるわ。子供は遊びを通じて柔軟に世界を広げていく。でも大人は知らず知らずのうちに競争や支配に囚われてしまう。その縮図を恐竜ワールドで見せているように思うの。
そんな中で登場するのが、戦士レプティラス。彼はこの恐竜ワールド最強の戦士として描かれていて、武器「スター・タロン」をいつも携えている。
彼が他の恐竜戦士たちと違うのは、彼には気高さがあること。仲間と同じように遊んでもらった経験はないから、自分が「おもちゃ」であることを知らないまま生きてきたの。
だからこそ彼は「戦士」という役割に完全に生きていて、自分をおもちゃではなく本物の戦士だと信じているの。これは一見すると誇り高い生き方に見えるけれど、同時に「おもちゃとして遊んでもらったことがない」という深い悲しみの裏返しなのだと思うの。
レプティラスは忘れ去られたおもちゃたちの象徴ね。でも彼の在り方は単純な悲劇には終わらない。なぜなら、彼はトリクシーと出会えたから。
トリクシーは自分の存在を恐竜として認めてもらえず、トナカイ役を押し付けられて悩んでいた。でもレプティラスの存在は、そんなトリクシーに強い影響を与えていく。
レプティラスたちの姿を見て、遊び心の大切さを改めて感じ取ったようね。レプティラスも、トリクシーを通して「遊び」という概念に触れていく。
おもちゃである以上、遊んでもらうことがどれだけ大切かを彼は知らなかった。でもトリクシーの存在が彼にその扉を開き始める。
彼の中に少しずつ「戦うことだけではない世界」が芽生えていくの。賢者クレリックがトリクシーやバズを快く思わなかったのは、彼らが「遊びの世界」の価値を持ち込むからだと思うの。
遊びの世界が広がれば、争いと支配だけで成り立っていた彼の世界は壊れてしまう。だからこそ、彼は必死に恐竜ワールドを支配し続けようとしたのかもしれない。
相関③|トリクシーの奔走とレプティラスの気づき
レプティラスとトリクシーの間に通じ合うものがあったわよね。でもその直後、戦場に立つレプティラスの姿は悲しいほどに冷たく、遊びという概念を一切持たない戦士のままだった。
彼は本来おもちゃでありながら、自分が「遊んでもらえる存在」であることを知らずに過ごしてきた。だから戦い続けることしかできない。
遊んでもらうことを通じて柔らかさや楽しさを知るチャンスを持たないまま存在してきた彼は、強さと孤独だけで自分を形づくってしまったみたいね。
そんな彼の姿を目の当たりにしたトリクシーは、何とかして彼らを救わなければと感じたのだと思うわ。トリクシー自身も恐竜として遊んでもらえないことに悩んでいた。でも、だからこそ「遊びを知らない悲しさ」を抱えるレプティラスに寄り添える気持ちが芽生えたのかもしれないの。
トリクシーはボニーのところへ助けを求めて走る。レプティラスをはじめとした「忘れ去られたおもちゃたち」を救いたい、その気持ちが彼女を突き動かしていたのだと思うの。
トリクシーを追って走るレプティラスにとっても、それは大きな転機になっていた。彼はこれまで「戦士」としてしか存在できなかったけれど、トリクシーを追いかける行動の中で、自分が「おもちゃ」として認識されるチャンスに出会うことになる。
一方で戦場に残されたボニーのおもちゃたちは危機に陥る。クレリックの手に落ちた彼らは完全にピンチの状態だった。そんな時、猫サウルス=エンジェルキティがまたしても一言を放つ。「人に与える喜びは自らの身に返るの」。短い台詞だけれど、重みがある言葉だったのかもしれないと思うわ。(笑)
与えることは損ではなく、巡り巡って自分の心を豊かにする。おもちゃにとって「子供に遊んでもらう」というのはまさにその実践なのかもしれない。
自分の時間や存在を子供に差し出すことで、子供の笑顔が返ってきて、それが自分の喜びになる。だけどクレリックはその言葉に「うざっ」という反応を見せていたの。
物語が動くのはここから。ピンチを救うにはレプティラスの変化が必要になる。これまで戦うことしか知らなかった彼に「遊び」という新しい可能性を教えること。
トリクシーがそれを担う役割を持っていたのだと思うの。彼女自身の悩みと彼の孤独が重なるからこそ、彼に気づきを与えることができたのだと思うわ。
遊びを通して存在を確かめるおもちゃの世界。その当たり前の真理に気づくことは、レプティラスにとって新しい誕生の瞬間だったのかもしれないの。
相関④|エンディングに響く言葉とおもちゃたちの幸福
物語の最後を飾ったのは、猫サウルスことエンジェルキティの言葉。「いつもあなたと共にある。神の恵みに感謝を」。もちろんいい言葉だし、学ぶべき言葉よね。でも、なんだか笑えて来るのがこのドラマの良さよね。
一連の騒動は戦いしか知らなかったレプティラスにとっては、自分が「おもちゃ」として存在する意味を受け入れる契機になったはず。誰かに与える喜びが自分に返ってくること。子供と遊ぶことで笑顔を生み出すこと。
その当たり前のようで見落とされがちな事実に気づいたとき、彼の中に「戦士としての孤独」ではなく「おもちゃとしての幸福」が芽生えたように感じるの。
思い返せば、自分が子供の頃にそこまでおもちゃに感謝を向けられていたかといえば正直あまりできていなかったかもしれない。ただ夢中で遊び、壊れてしまえば忘れてしまう、そんな扱いだった気がするわ。
忘れ去られたおもちゃの世界に光が差し込んだのは、トリクシーが「遊びの世界」を伝えたからだったの。そしてレプティラスがそれを受け入れたことで、争いに閉ざされた恐竜ワールドに光が差し込むことになったわね。
まとめ
20分足らずの短編ながら、ボニーの奔放なごっこ遊びから、忘れ去られた恐竜おもちゃたちの孤独、レプティラスの誇りと悲しみ、そしてトリクシーの勇気ある行動まで、濃密なテーマが詰め込まれていたと思うの。特に印象的なのは、遊びを知らず戦いに囚われていたレプティラスが、トリクシーとの関わりで「おもちゃとしての幸せ」に目覚めていく姿。その背景にはエンジェルキティの哲学的な一言が効いていて、「人に与える喜びは自らの身に返る」という言葉が物語全体の芯を作っていたように感じるの。
今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

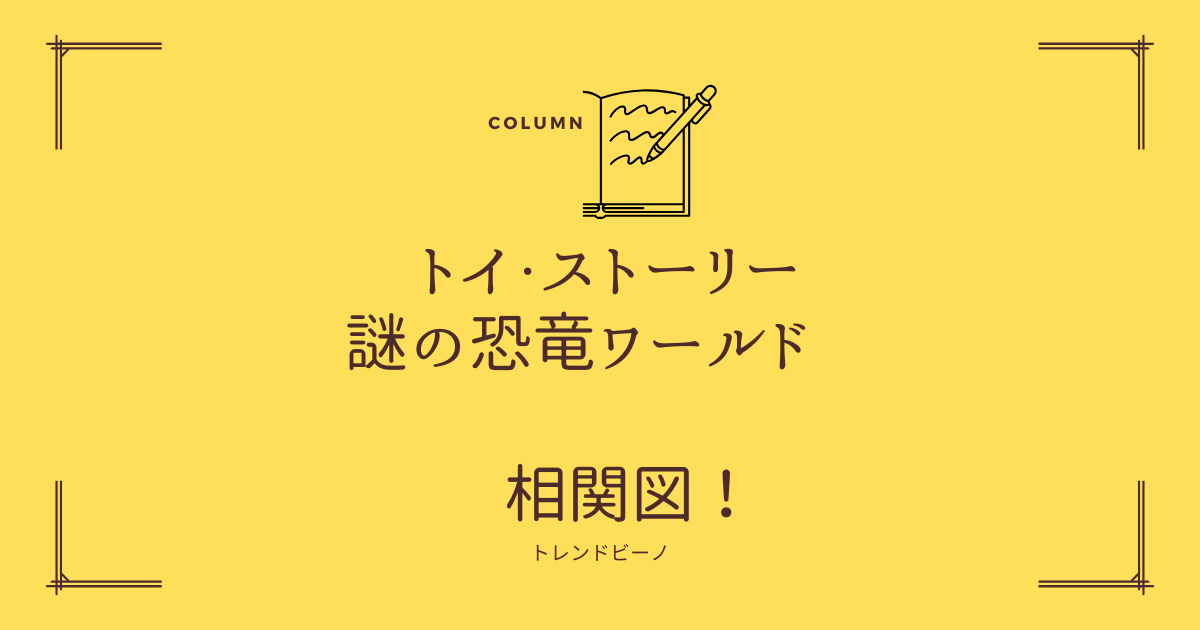
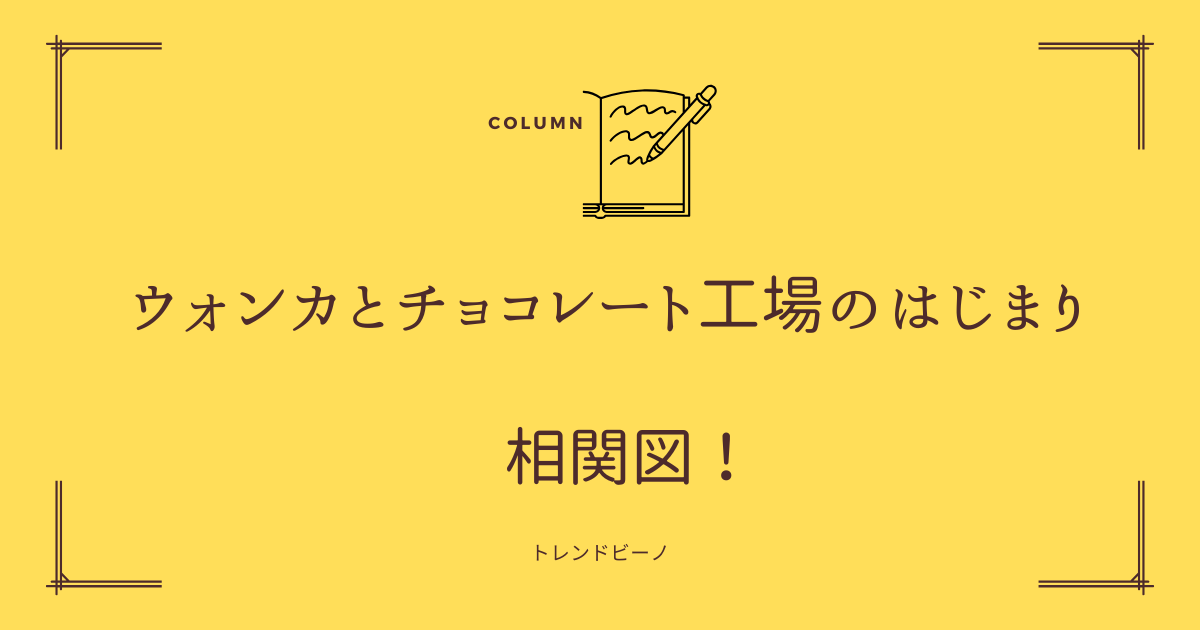
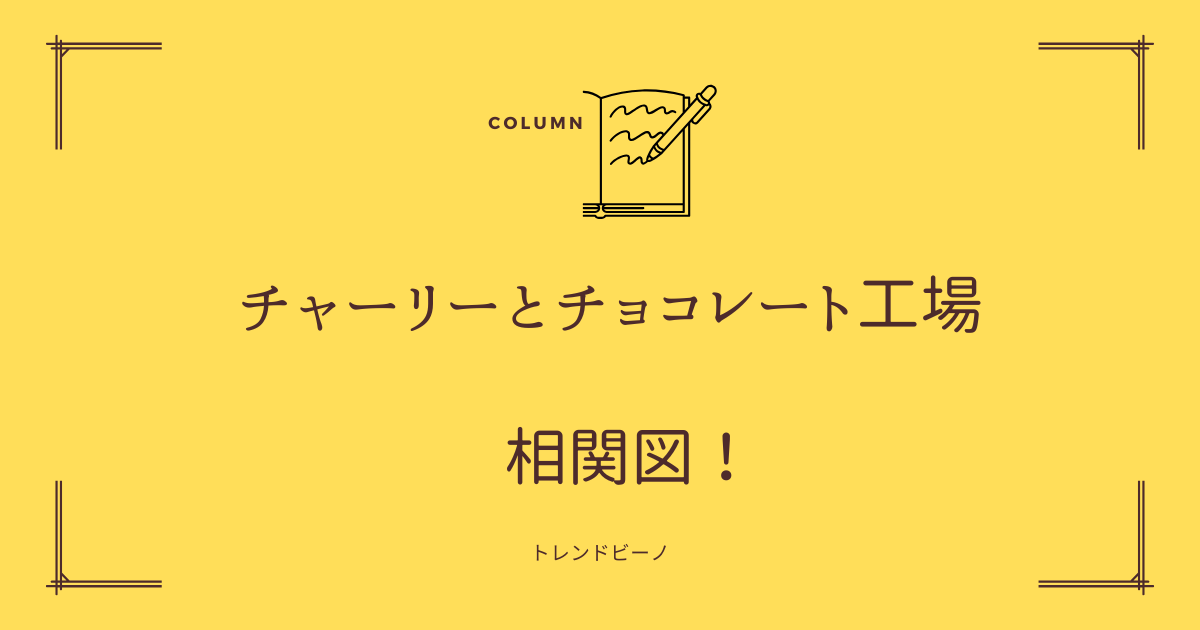
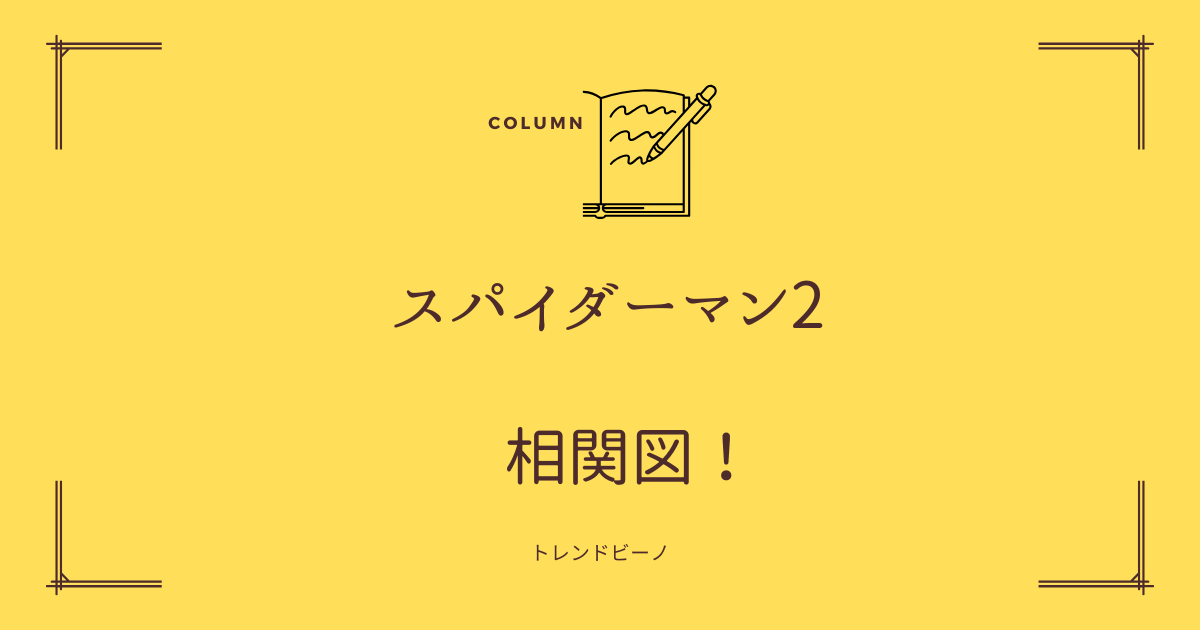
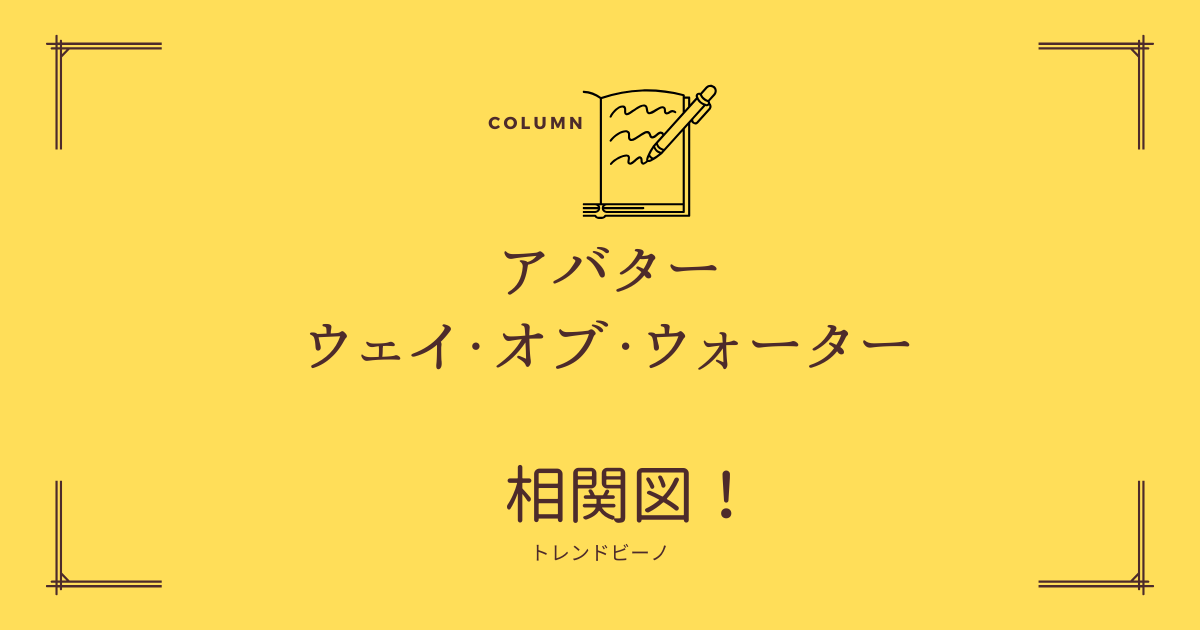
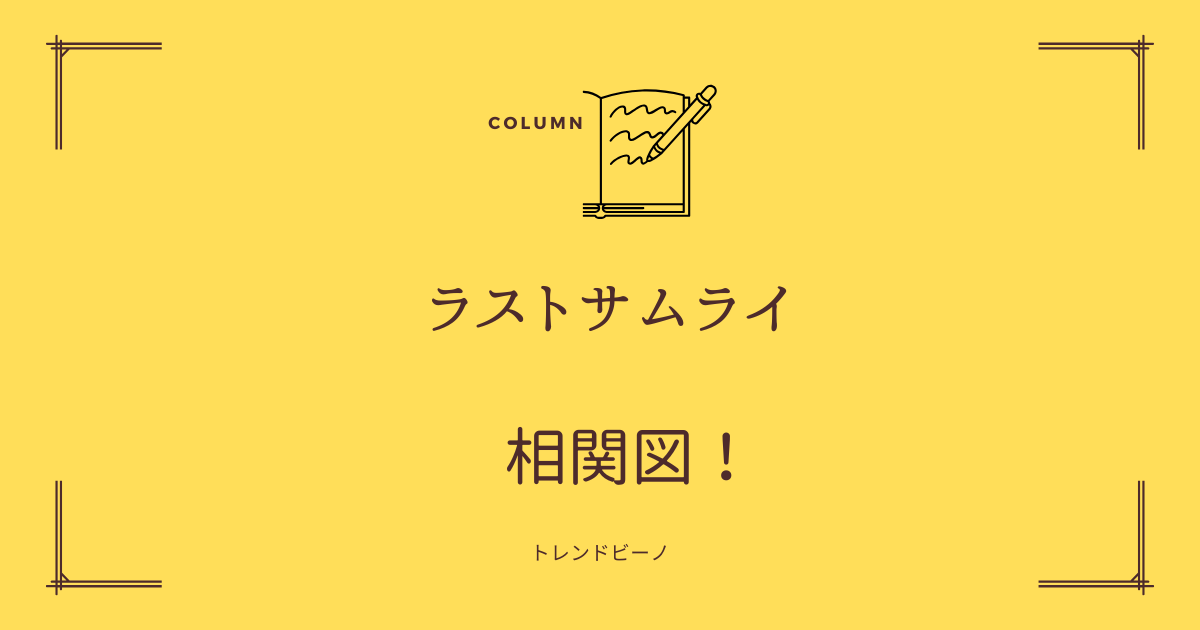
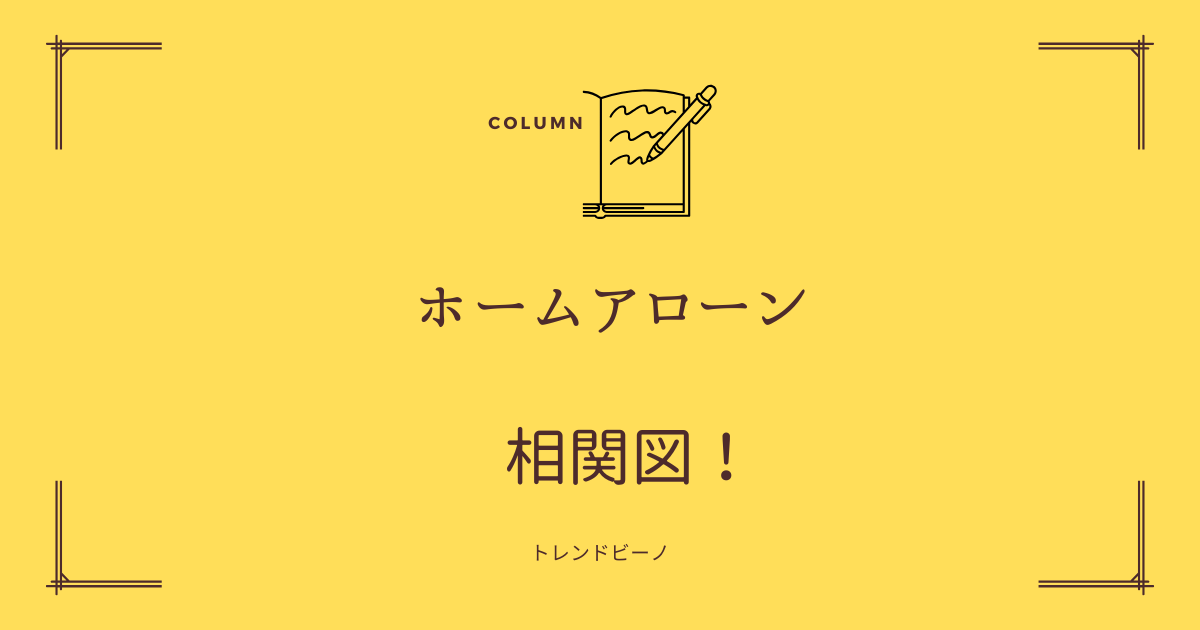
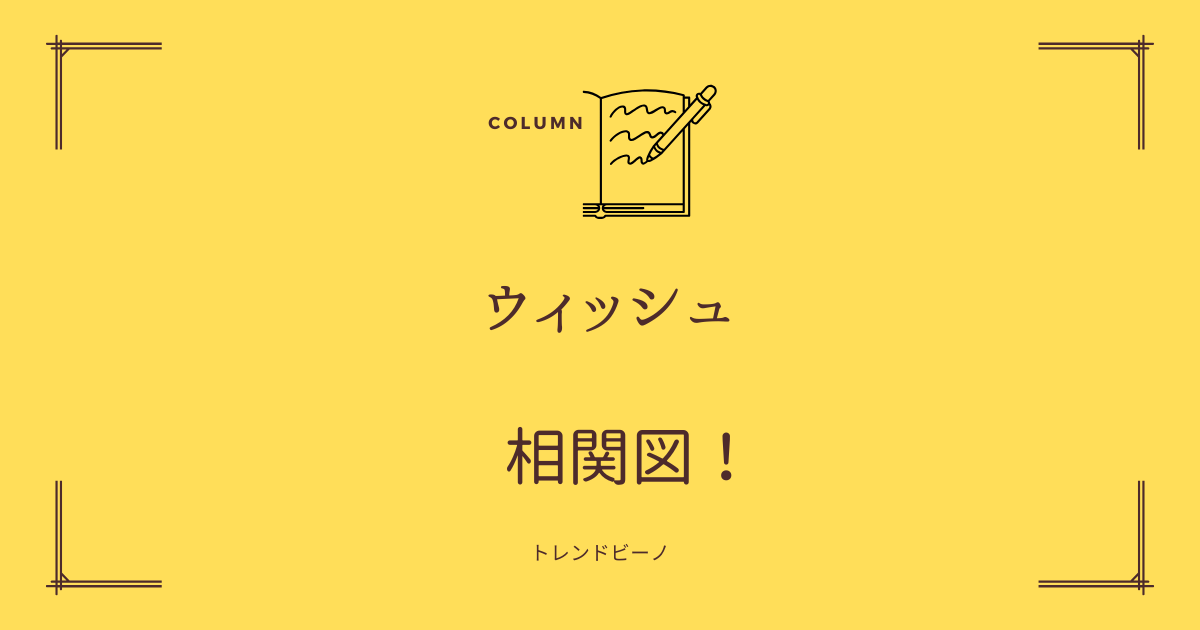
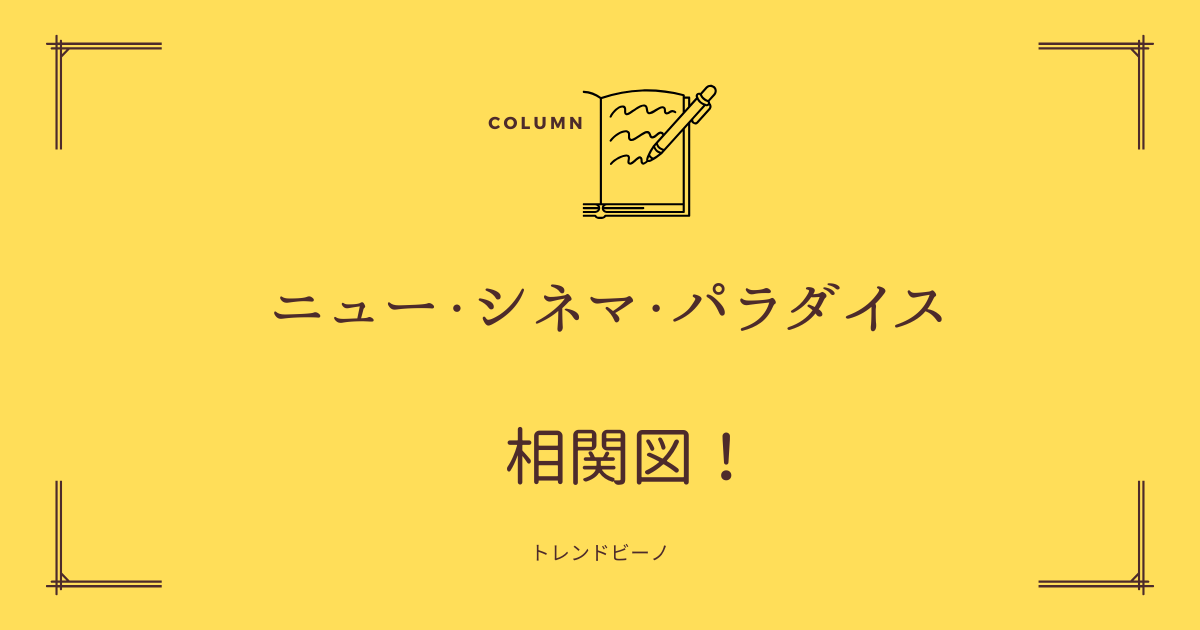
コメント