映画『ミッション:インポッシブル/ゴーストプロトコル』のタイトル、ちょっと意味深ですよね?「ゴースト」と「プロトコル」。一見カッコいいけど、これって一体どんな作戦名なの?という疑問、抱いた方も多いのでは。
この記事では、そんな「ゴースト・プロトコル」の意味をじっくり掘り下げてみます。映画内の状況やセリフの裏に隠された本当の意図、そしてイーサン・ハントの“もうひとつの戦い”についても深掘りしていきますよ〜!
ゴースト・プロトコルとは何だったのか?|言葉の意味と発動の背景
まずは言葉の意味からしっかり見ておきましょうね。
「ゴースト(ghost)」は、“幽霊”──これは分かりやすい。でもね、英語圏では「存在していたのに、なかったことにされる」「無視される」「消される」って感じの意味も持ってるんです。
そして「プロトコル(protocol)」は、「手順」や「規定」、あるいは「緊急時の対応マニュアル」なんて意味もある。
つまり、「ゴースト・プロトコル」って、「存在してたはずのものをなかったことにする手順」──そんなニュアンスなんです。
劇中では、爆破事件のあと、アメリカ政府がIMF(イーサンたちのスパイ組織)の存在を否定。「我々は関与していない」「そんな組織は知らない」と言い出すんですよ。はい、バッサリ切り捨て。
その瞬間に発動されたいたのが「ゴースト・プロトコル」。要するに、「責任を取らずに済ませるために、組織ごと幽霊化します」っていう、かなりドライな非常措置だったんですね。
これ、なかなかの冷たさ。だけど、この冷酷なスタートが、物語全体のトーンを決めてるんですよね。
因みに、それ以前にイーサンが刑務所にいた理由も気になる方にはこちらもどうぞ!
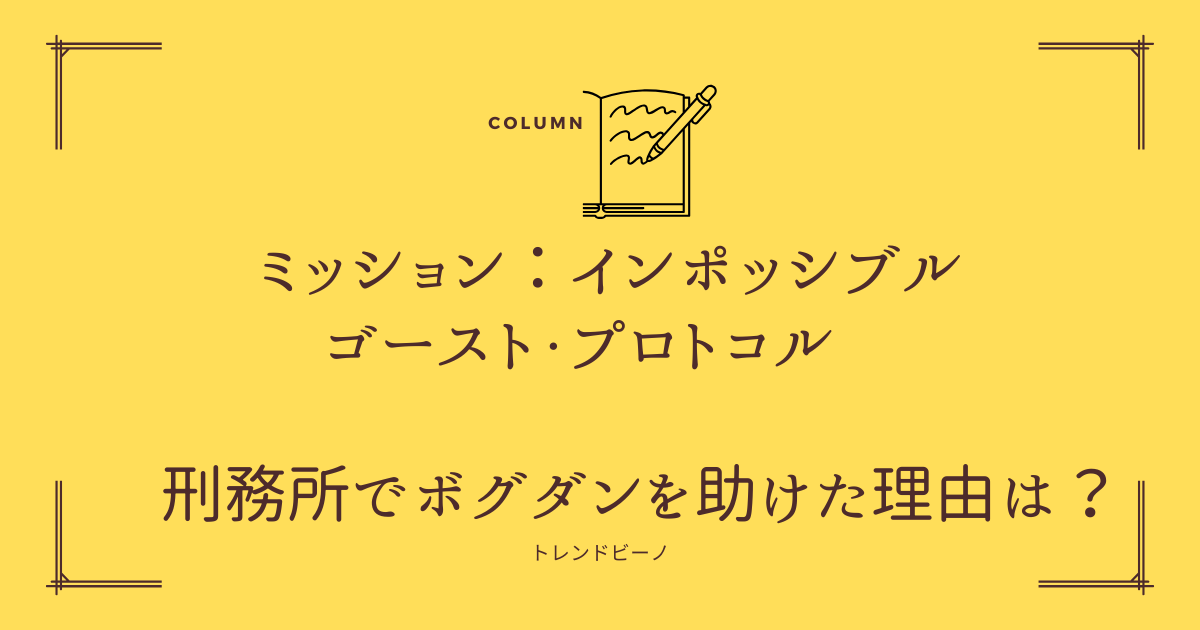
ゴーストプロトコルの発動で、それは既に「任務」ではなくなった
ここ、大事なところですよね、
この時点で、イーサンたちに「任務」はありません。だって、国家からの命令は切られてるし、装備もサポートもゼロ。「勝手にやって。何が起きても知りませんから」って、完全に放り出されてるんです。
そんな中、イーサンたちはどうしたのか?──動いたんです。「え、なんで?」「命令ないのに?」って思いますよね。そう、彼らは“動くしかなかった”んです。
敵はミサイル発射をもくろみ、世界の破滅は目の前。でも、それを止める術があるのは自分たちだけ。だったらやるしかない──もう、それだけだったんですよね。
この行動、もう“任務”なんて呼び方は似合いません。これは完全に“信念”で動いてる。国家の後ろ盾なんかなくたって、命を懸けてでも止めなきゃいけないことがある。
スパイっていうより、友として、人としての責任感。ここが、ぐっとくるんですよね。
ハンドジェスチャーの意味!あの目配せにすべてが詰まってる?ムンバイでの「証人作戦」
そして、ムンバイのあのシーン。イーサンが、ロシアの諜報員シディロフに“わざと”見られるように立ち回るところ、見逃してませんでしたか?
あれ、「あ、偶然見つかった」ではないですし、単なる挑発でもなさそうです。あれはもう、完全に“見せてた”──「俺たちはやってない。世界を救うためにここにいるんだ」と伝えるための、無言のアピール。
ボグダンに「何としてもドバイまで連れてこい」って言っていたのは、きっと従兄弟の事なんですよね。そして、そのボグダンの従兄を使ってやりたかったことは二つ。ヘンドリクスが衛星を入手する方法を突き止めることと、あと一つ。
そう、イーサンは“証人”を作りたかったんですよ。きっと、従兄弟はシディロフともつながっていることをどこかで察知していたのではないかなとおもうのです。
ロシアがIMFへの疑念を解いてくれれば、アメリカも「IMFをなかったことにしておく必要がない」ってなるわけです。
この構図を、イーサンは完全に読んでた。爆破を止めることと同時に、“IMFが復活できる地ならし”まで仕込んでたんんじゃないかと思うのです。
この“証人作戦”の裏にあったもうひとつの仕掛けはこちらで詳しく!
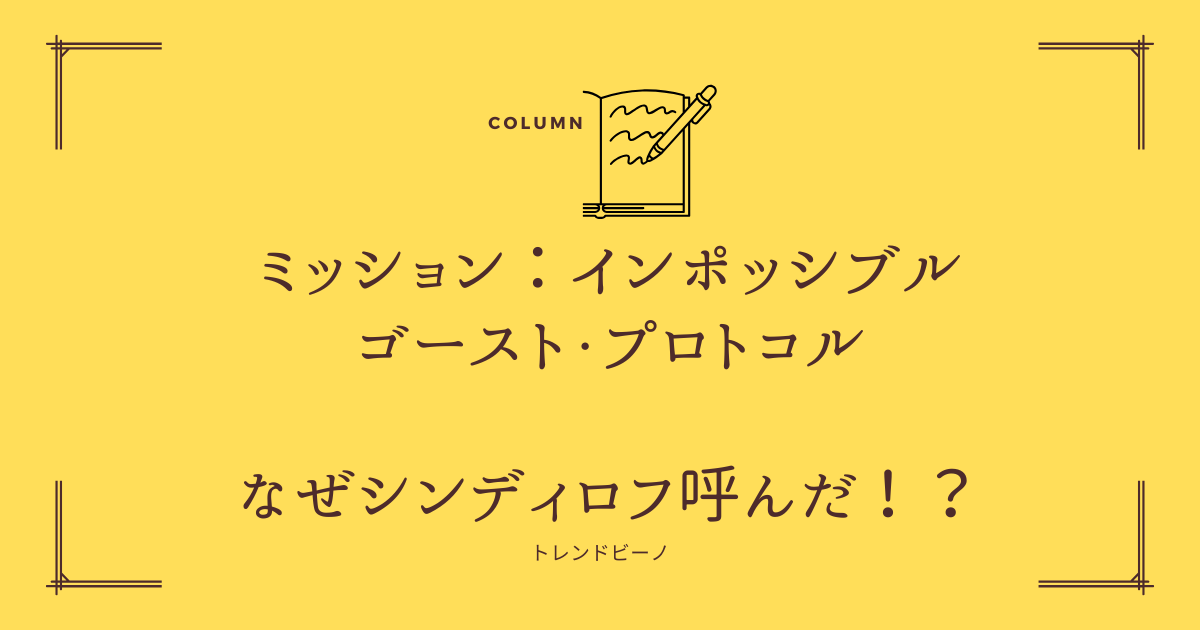
“切り捨て”じゃなくて“元に戻す準備”?プロトコルの裏の二重構造
さてさて、この「ゴースト・プロトコル」、実はタイトルからして、かなり皮肉の効いた二重構造になっているようにおもうのです。
まずひとつは、IMFという組織を見捨てて国家の責任を回避する、公式なプロトコル。これは表向きの意味。
でもね、実際のところはどうかというと──
「いったん消えはしたが、後で何としても戻したるねん」っていう、イーサンの執念がこもったタイトルのように感じるのです。つまり、ゴーストプロトコルを発動したということを、“なかったことにする”という二重構造。
イーサンはボグダン救出の時にはそういった事態を知らなかったはず。にもかかわらず、後に超キーパーソンとなるボグダンを救出し、従兄弟につながっていくあたりが、イーサンの人徳なんだろうなと一人感心したりするのです。
「ゴースト・プロトコル」は、国家の都合によっても決してつぶされることのない、イーサンの信念のようなものを感じますよね。
ゴースト・プロトコル以降、IMFはどうなった?
で、その後の展開は、イーサンが思い描いていた通りなのではないでしょうか。
『ゴースト・プロトコル』のラストでは、イーサンの元に“次の指令”が届きます。え?復活してるやん!って思った人、多かったはず(笑)。そう、IMFはちゃっかり“復活”してるんですよ。何事もなかったように。
でも、そこから先もまた波乱続き。次作『ローグ・ネイション』では、CIAに「IMFって危険なんじゃないの?」と疑われ、吸収・解体の危機に直面。その後『フォールアウト』では、イーサンたちの活躍によって再評価され、やっと組織として独立を取り戻します。
そして『デッドレコニング PART ONE』では、またしてもとんでもない脅威(AIエンティティ)に立ち向かう中で、IMFは再び「最後の希望」みたいな存在に返り咲きます。
消されたり、戻ったり──まるで本当に“幽霊”みたいな扱い。
この不安定なIMFの運命を背負ったイーサンの原点とは?刑務所編はこちら
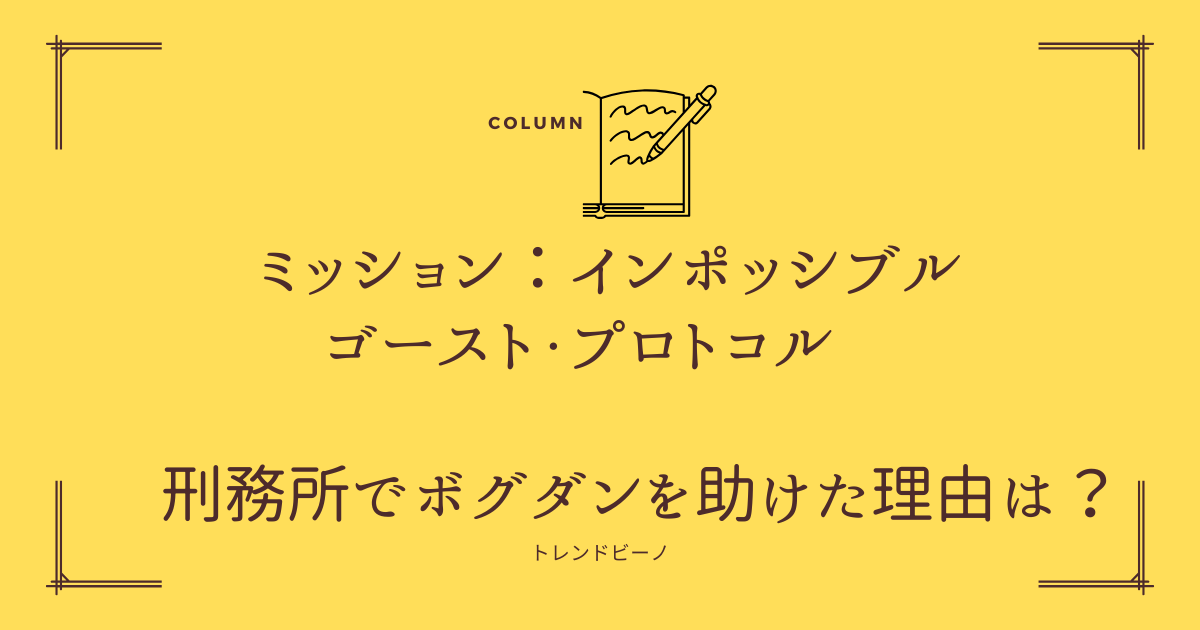
まとめ|イーサン・ハントは信念でうごいた末に世界を守り、IMFの復活まで成し遂げた
最初は「任務も仲間も失った男が、世界を救う」って話かと思って観てたけど──実は違った。イーサンは、ただのスパイじゃなかった。
世界を救うだけじゃなく、IMFという組織の“価値”を守るために、あえて証人を立て、地ならしまでしてた。もう、スパイとかそういう次元じゃない。国家の都合と真っ向から向き合って、護るべきものを守った。
その結果、IMFは“しれっと”復活。「消えたはずのプロトコル」は、いつのまにか“なかったこと”になってました。
──まさに、ゴースト。イーサン、あんた……かっこよすぎるよ。
今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

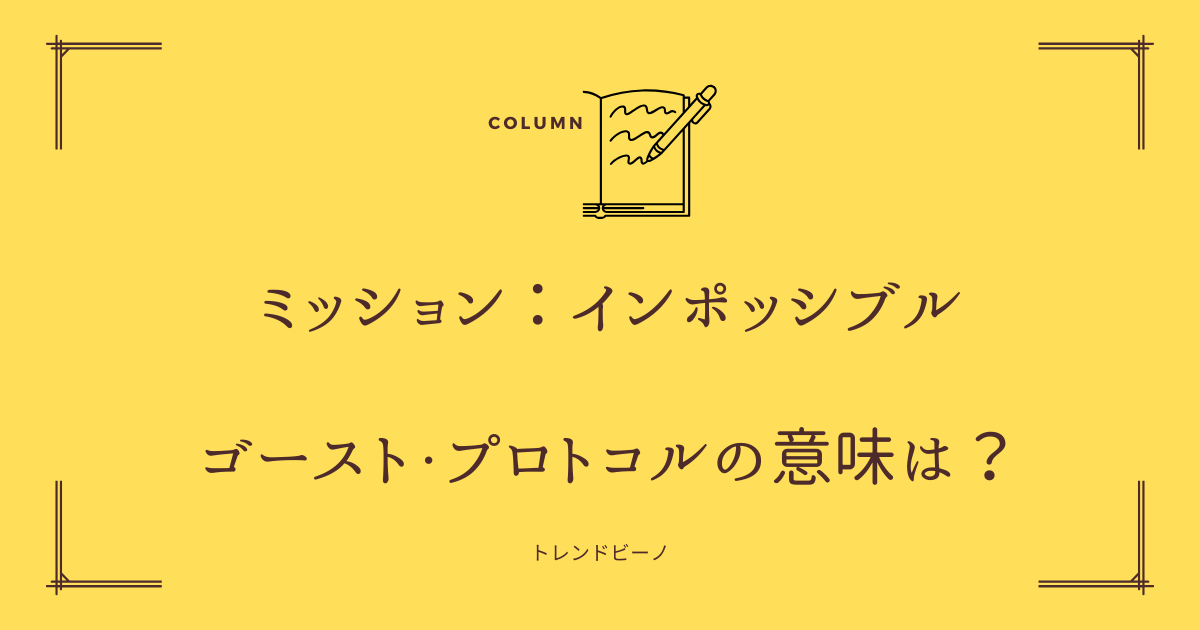
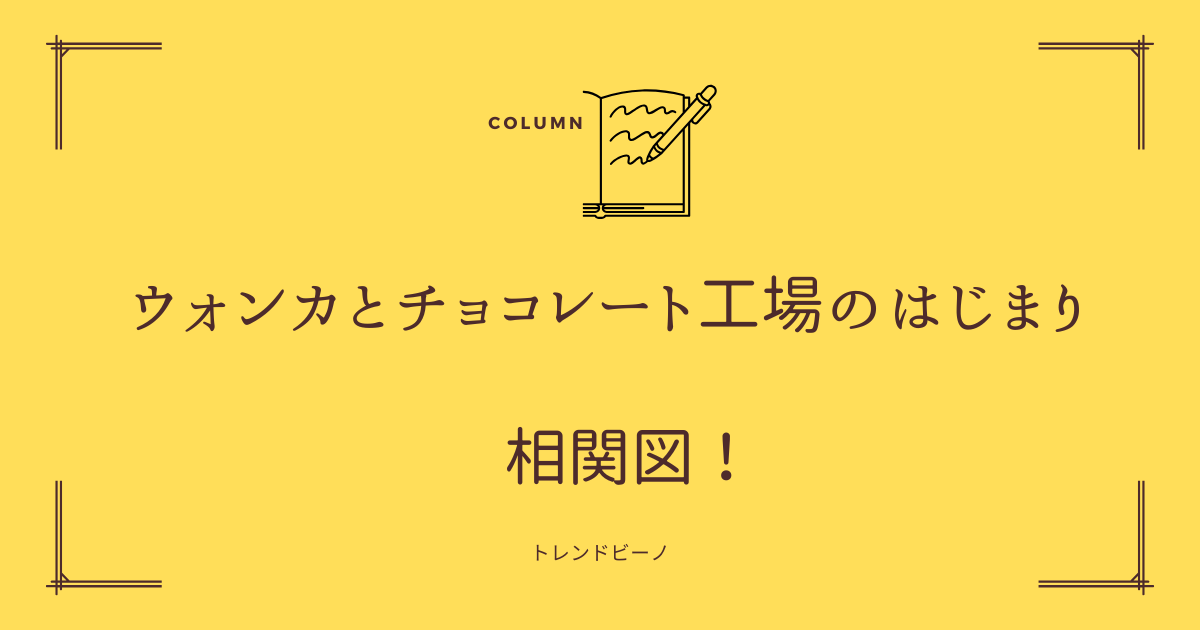
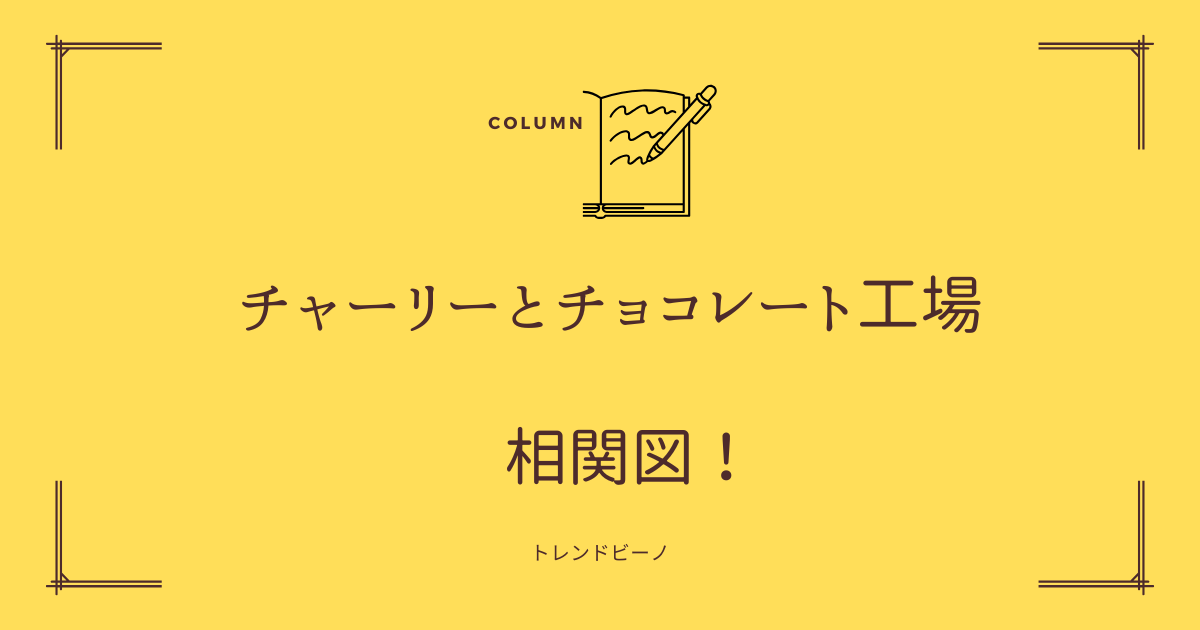
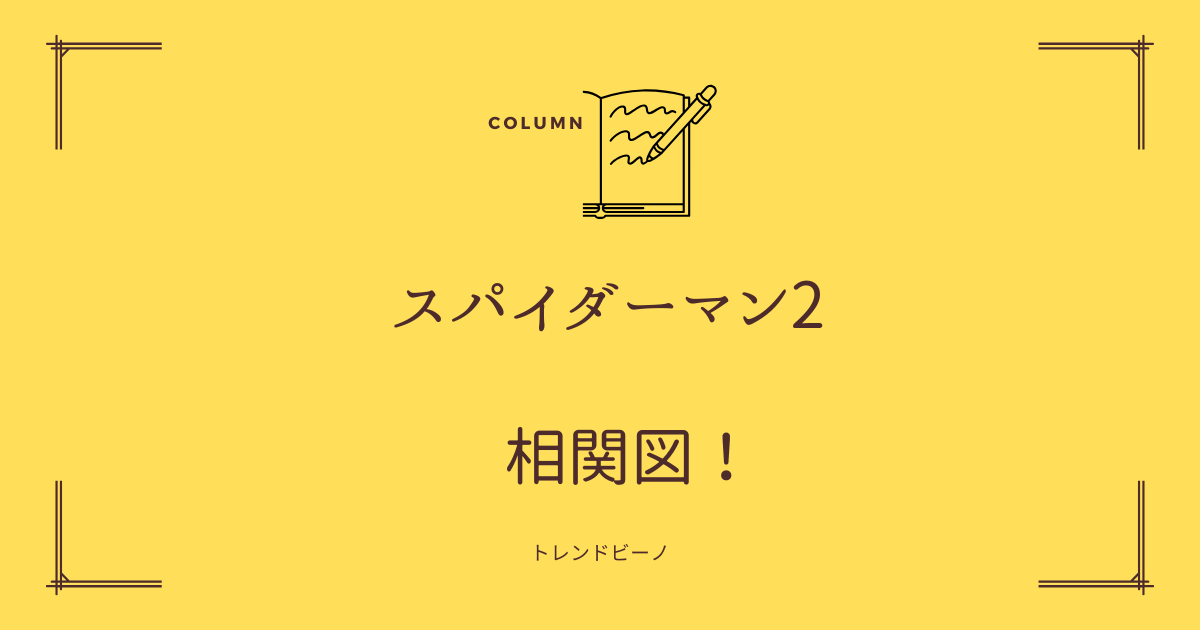
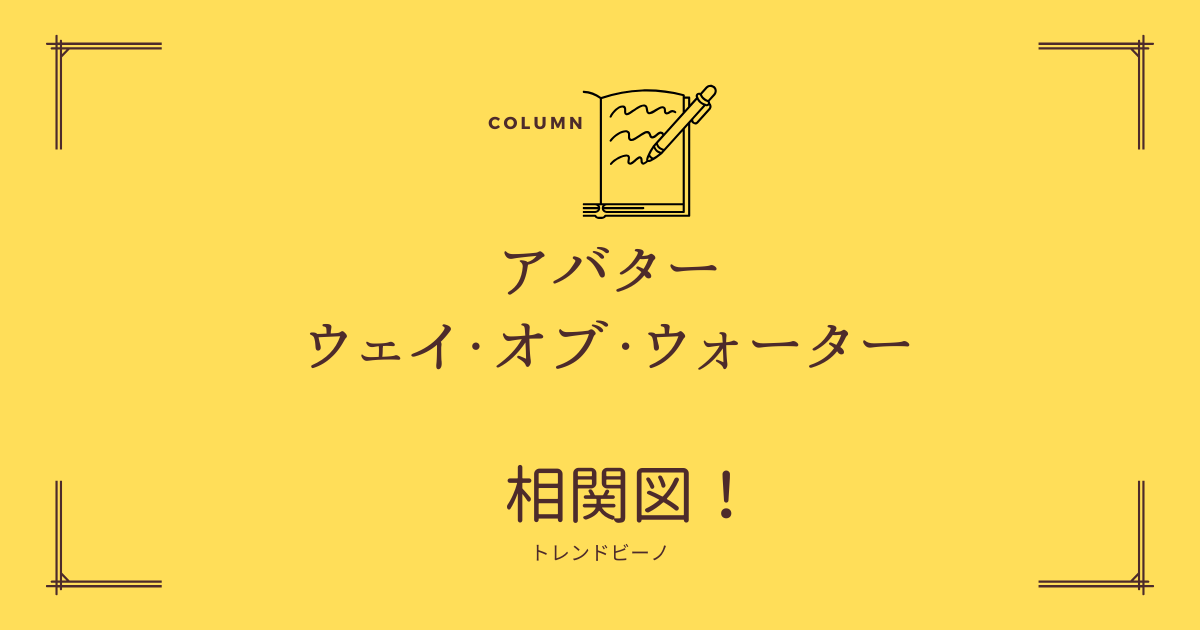
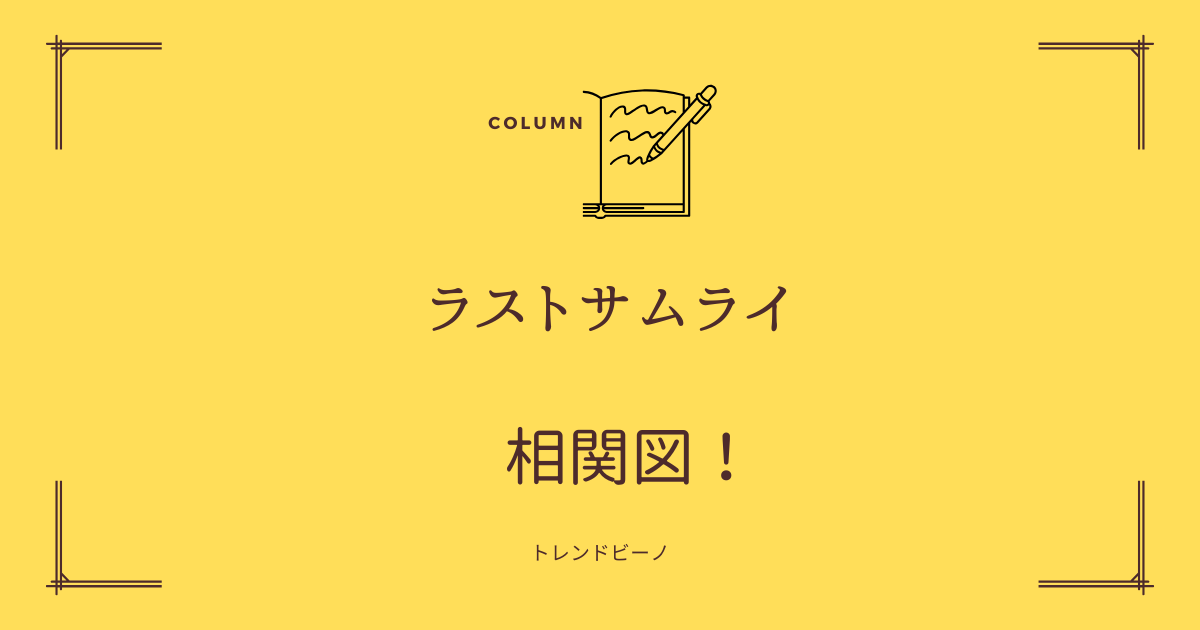
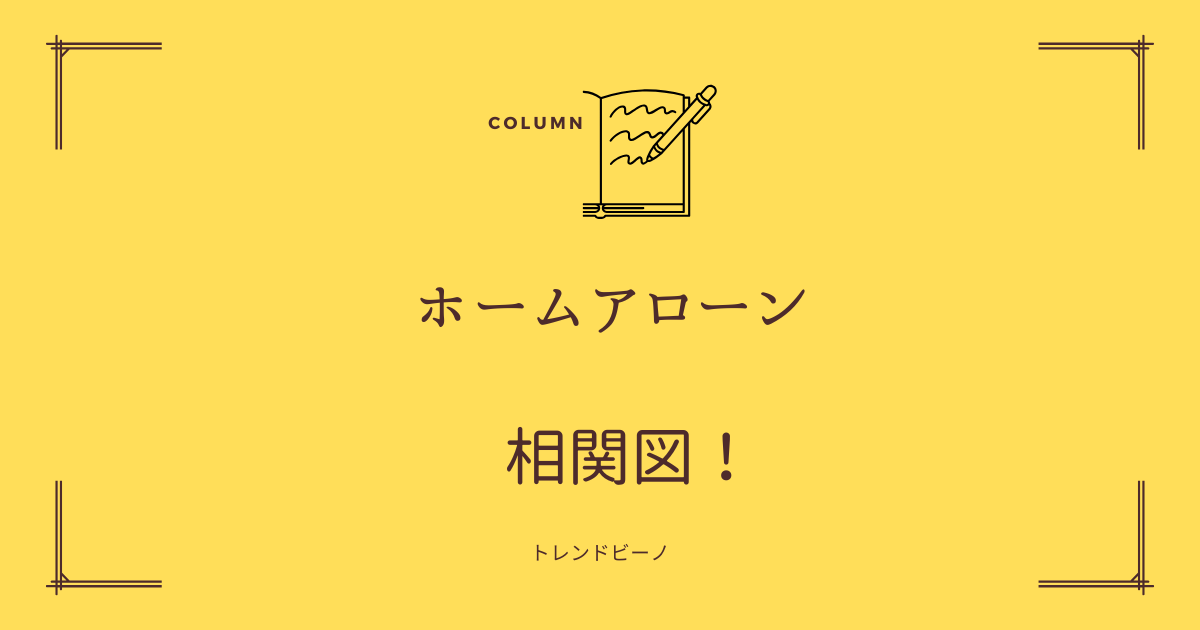
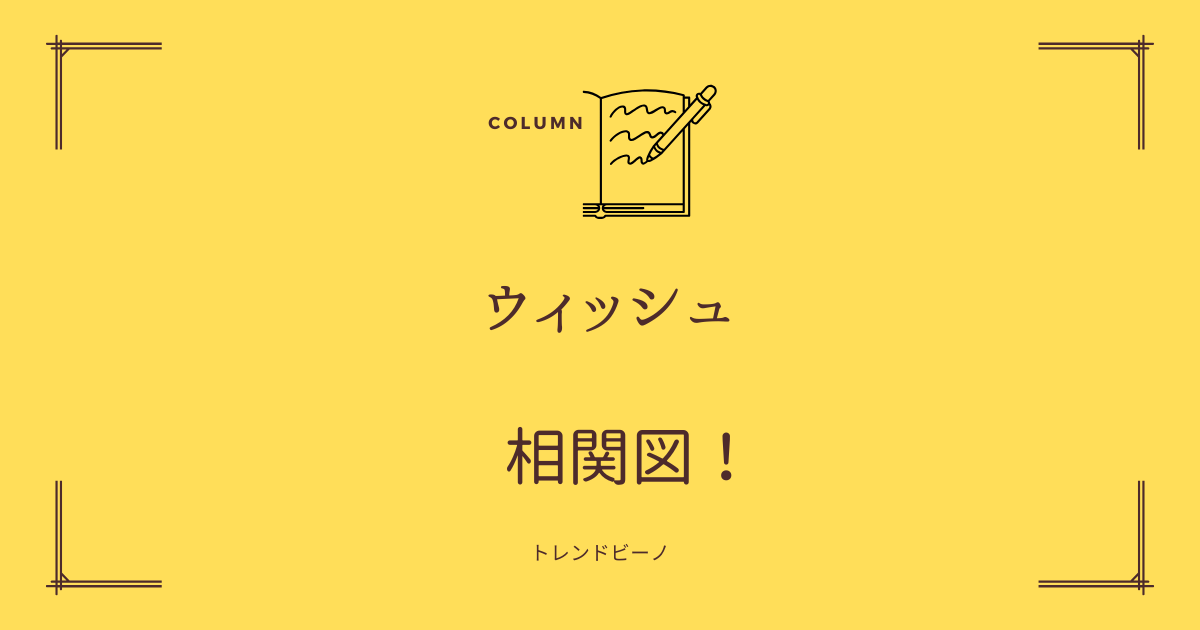
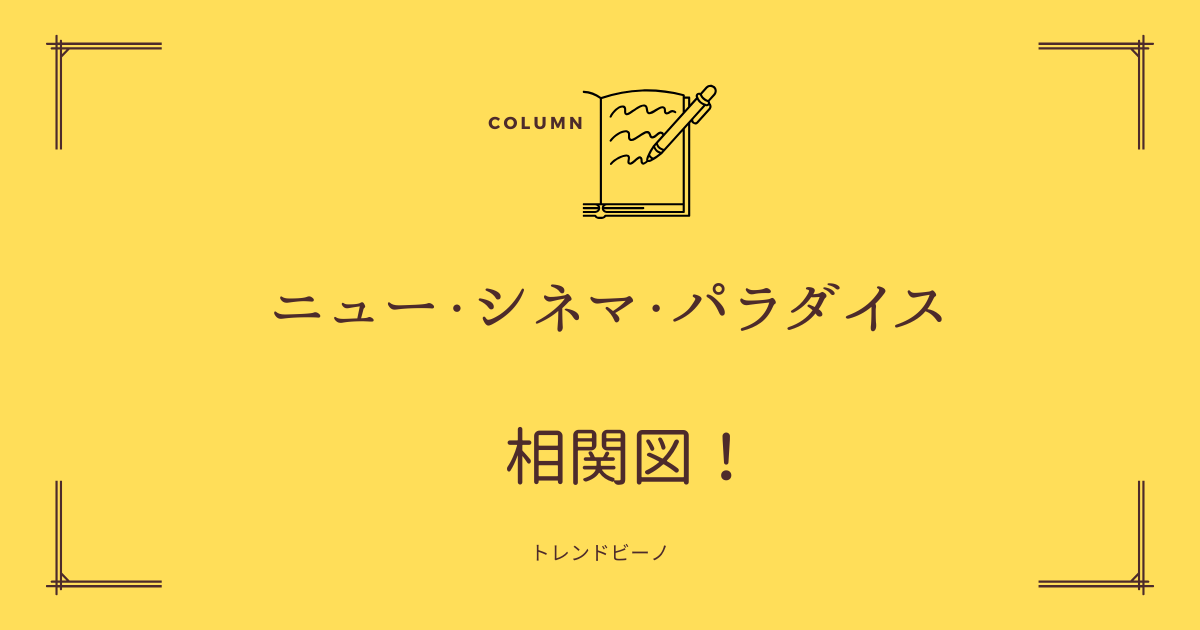
コメント