ジブリの『君たちはどう生きるか』、タイトルの時点でもう深そうだな〜って思ってましたが、実はこのタイトル、映画の中に登場する本の題名といっしょなんですよね。
「大きくなった真人君に」なんて意味深なメッセージも出てくるし、母・ヒミの正体も不思議すぎるしで、頭がこんがらがった方も多いんじゃないでしょうか?(私もです!)
今回は、「本は実在するの?」「母が遺したメッセージの意味は?」「なぜヒミは眞人を忘れてたの?」といった疑問を、じっくり考察してみたいと思います♪
『君たちはどう生きるか』の本は実在する?|映画と原作のつながりを解説
まず結論から言うと、『君たちはどう生きるか』という本は実在します!1937年に吉野源三郎さんという方が書いた児童文学作品で、近年は漫画版も大ヒットしていたので、書店で見かけたことがある方も多いかも。
内容はというと、いじめ、貧困、不正義…そんな社会の現実を目の当たりにした中学生の“コペル君”が、自分の生き方について悩み、成長していく物語。そこに叔父さんとの手紙のやりとりが挿入されていて、まさに“どう生きるか”を考える哲学的な構成になっています。
ただし!宮崎駿監督の映画とは、ストーリーもキャラクターもまったく違うんです。でも「少年が心の旅を通じて、世界の真実と自分の生き方に向き合う」――という“精神的なテーマ”(?)について取り上げたという点に関しては、共通点ありといえるかもしれませんね。
実際、映画の中に、ヒサコから眞人への贈り物として登場するわけですから、それだけでも相当なご縁はかんじますよね。
母から眞人への贈り物「大きくなった眞人君に」の意味とは?
火事で亡くなった母が残したのが「大きくなった真人君に」という言葉でしたよね。あれ、ちょっと泣きそうになりませんでした?(私はなった…)
でも、少し違和感が残ったのは、あの言葉が与える印象は、自分が成長した眞人を見守る時間はもう残されていないということを知っている人の言葉のように感じたからなんです。
私の頭に思い浮かんだのは二つ。火事が起こったときに「病院のかあさんが」と言っていたと思うんです。それを聞いたとき、最初に浮かんだのは、病院に勤務していらっしゃるんだろうなというイメージです。なので、このメッセージは違和感を伴ったんですね。
でも考えてみると、2つ目の可能性として、患者さんとして病院にいらっしゃったという可能性。これなら、ほんの裏表紙に眞人へのメッセージを残すという必然が生じるように思います。ただ、それも次の瞬間にはいや違うだろっていう思いに打ち消されます。
なぜって、ヒサコの元となっているヒミの性格からして、病気とは無縁の感じしかしないんですよね。いつも明るく朗らかにしていそうなヒミの性格と病気のイメージが同居できないんですよね、管理人の感じるところでは。
そんなことを考えていると、もう一つの可能性が頭に浮かんできました。それは、「やはり、ヒミ(ヒサコ)は特殊な存在(神がかった)」だったという設定です。
青サギは言っていました。「普通この上の世界に来たら、下の世界のことは忘れているものだ」と。でも、眞人は覚えていたんですよね。ポケットに忍ばせた、下の世界の白い石のせいかもしれませんけど、それでも、眞人は普通は覚えていられないことを覚えていたという特殊な存在。
眞人が感じた母ヒサコが火災の中から眞人に呼びかけている言葉、それは救助を求めるわけでも、その状況を悲劇的に訴えるものでもありませんでした。私が感じたのは、ただ、またしばしの別れをちょっと寂しく思う母の気持ちが眞人に伝えられたような。
つまり、普通は覚えていないであろう過去での出来事、母や夏子を捜し歩いた眞人に出会い、眞人から「母さんは家事にあって死んじゃう」ということを聞いていたヒミ。ヒミはそのことを覚えていたのではないでしょうか?
さらにヒミは下の世界では、炎と共存できる特殊性を持っていました。下の世界に登場した人物が皆そういった特殊性を持っているかと言えば、キリコは普通でしたし、あの大叔父ですらそういった身につけた特殊能力という点では、特別なものを感じさせることはありませんでした。
さらにヒミは、ワラワラを食らおうとして舞い上がるペリカンを、自らが放つ炎によって追い払ったり、明らかに特殊な仕事(?)や能力をもっていました。
そんなことから、本に書かれたヒサコの言葉は、眞人としばしの別れが来ることを知っていて、伝えたいことはたくさんあるんだけど、残された時間はおおくない。だから、人としての愛とか生き方を学びつつある眞人に、一番適したテキストとして、あの本を送ったのかな。そんな気がしています。
眞人とヒミが“時を越えて出会った”意味や、彼女の特異な性質の考察はこちら
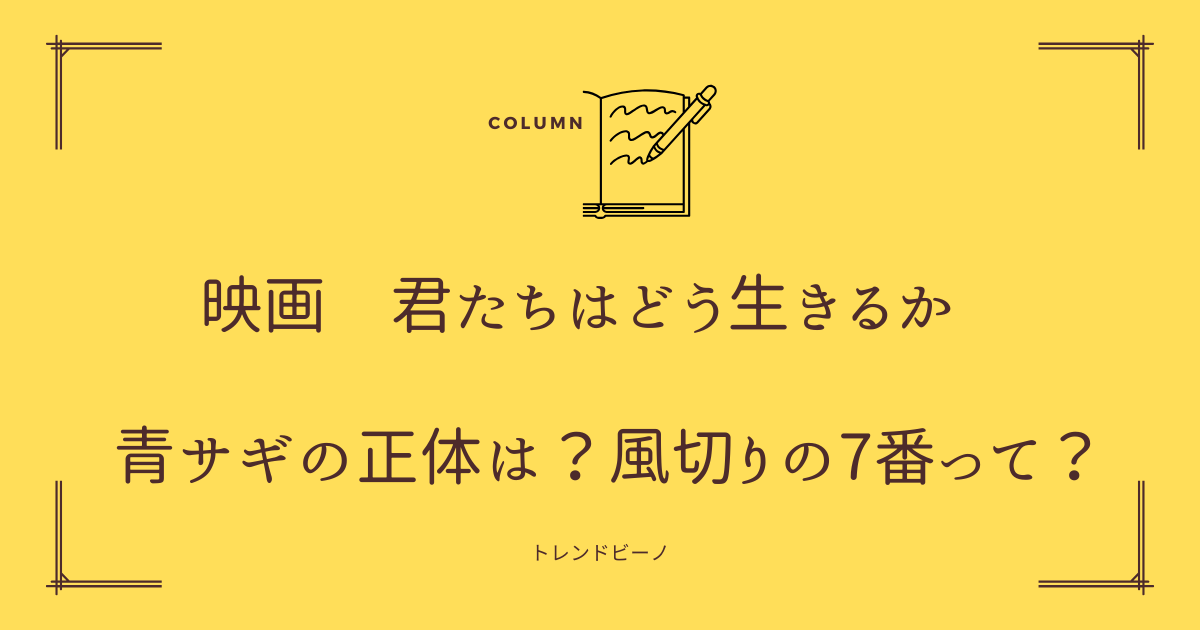
なぜヒミは眞人を思い出せなかったのか?|“時を超えた出会い”の謎
映画を観ていて混乱しがちなもう一つがここ。眞人が出会ったヒミって、後の“母”なんですよね?でも、ヒミの方は眞人を見て「あなた誰?」状態。なぜ気づかなかったのか。
それはズバリ、眞人は“未来から過去へ”来たけど、ヒミはまだ“その未来”を知らなかったからなんでしょうね。
つまり、ヒミにとって眞人は「まだ生まれていない子ども」。
しかも、眞人が来た世界はおそらく“夢”のような構造を持つ下の世界。ヒミだけは過去から来たんじゃなくて、**あの場所に“もともといた特別な存在”**ということかなとおもうんです。もしかしてもしかしてですが、眞人に向かって「お前いいやつだな」みたいな言葉をかけるシーンがありましたが、ずっと下の世界にいたヒミですが、眞人とあそこで出会ったことで、「この子を産みたい」みたいな気持ちが芽生え、上の世界にいっとき行くことをきめたのかも。。。。多少の矛盾も抱えながらという気はしますが、そんな妄想が私の頭の中を駆け巡っています。
ヒミの正体は誰だった?|“火と神話”の中に生きる存在として
改めて、ヒミって、ちょっと不思議な存在でしたよね。名前も特別っぽいし、何より火事の中で亡くなる時も、慌てたり悲鳴を上げたりしない。なんか、どこか達観したような、別の次元にいるような…。
実はヒミって、“火”と深い関わりがあるキャラクターだったんじゃないかと私は感じています。たとえば、火=再生、火=浄化、火=魂の旅路…って、神話でもよく登場するモチーフですよね。
ヒサコはヒミの記憶を忘れて上の世界で生活していたのか、或いはヒミの特別性がゆえに下での出来事もしっかり覚えていたのか、私の中では定かではありません。でも視聴後に振り替えると、ヒミの行動は、眞人にジャムを塗ったパンをあげているところ以外は、あの世界を熟知し、特殊能力も発揮するという、どこか神がかった存在として描かれていたように感じました。
火事の描かれ方が冷静だった理由|ヒミの静かな覚悟と未来への旅立ち
ヒミが亡くなるシーン、驚くほど静かだったように感じました。悲鳴もなく、慌てる様子もなく、ただ眞人に言葉を残して炎に包まれていく――まるで“自らの運命やどこから来てどこに戻るのかを知っているようにすら見えました。
眞人と下の世界で出会い、未来を垣間見たヒミは、自分の肉体の“死”すらも愛と赦しの視点で受け入れていたんじゃないでしょうかね。
火の中に消える姿は、恐怖ではなく、“未来へ向かう静かな旅立ち”だったんじゃないかな。それに、ヒミは特別な魂を持つ存在だった――火とともにある者。そんな印象も受けますよね。
このシーン、派手な演出はないのに、静かに胸を打つ…。
「このシーン、もう一度見返してみて!」と言いたくなる美しさと深さが詰まっていたように思います。
まとめ|“生きる”とは、見えない想いを受け取ること
『君たちはどう生きるか』というタイトルに込められた意味。それは、単に哲学的な問いかけではなく、「誰かの愛を、どう受け取って、どう応えていくのか」という物語だったんじゃないでしょうか。
母が残した「大きくなった真人君に」の一言。そして眞人が選んだ「友達を探す」という道。
どちらも、本という“形”ではなく、“心”に残るメッセージでした。たとえ本が登場しなくても、この映画そのものが、現代の私たちに向けた「新しい君たちはどう生きるか」だったのかもしれませんね。
今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

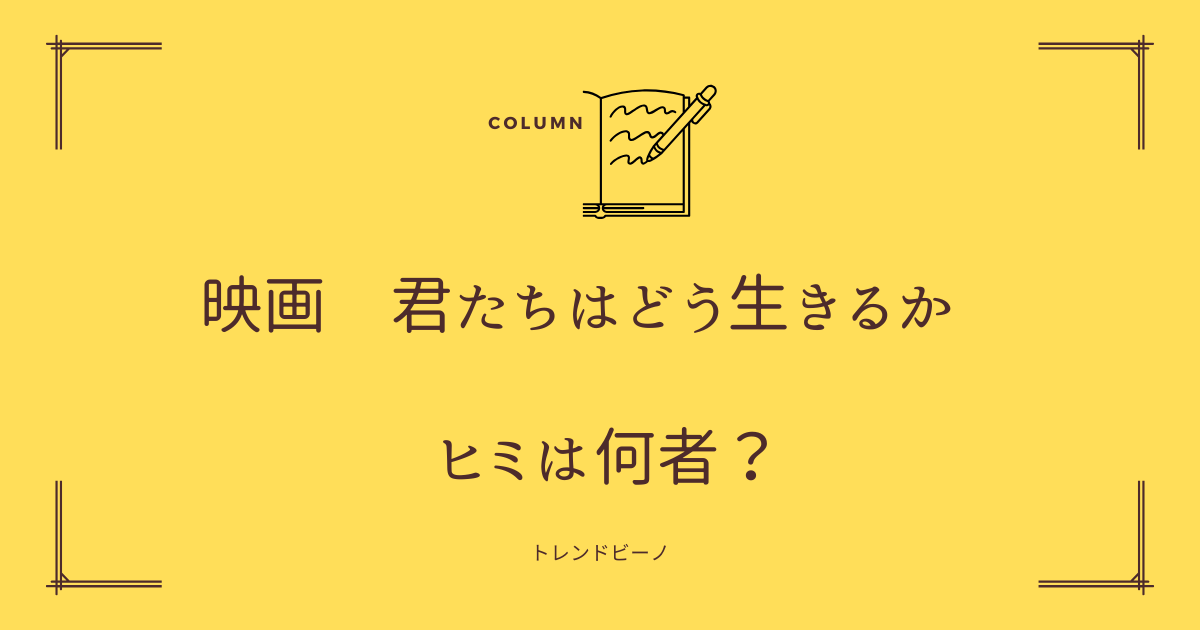
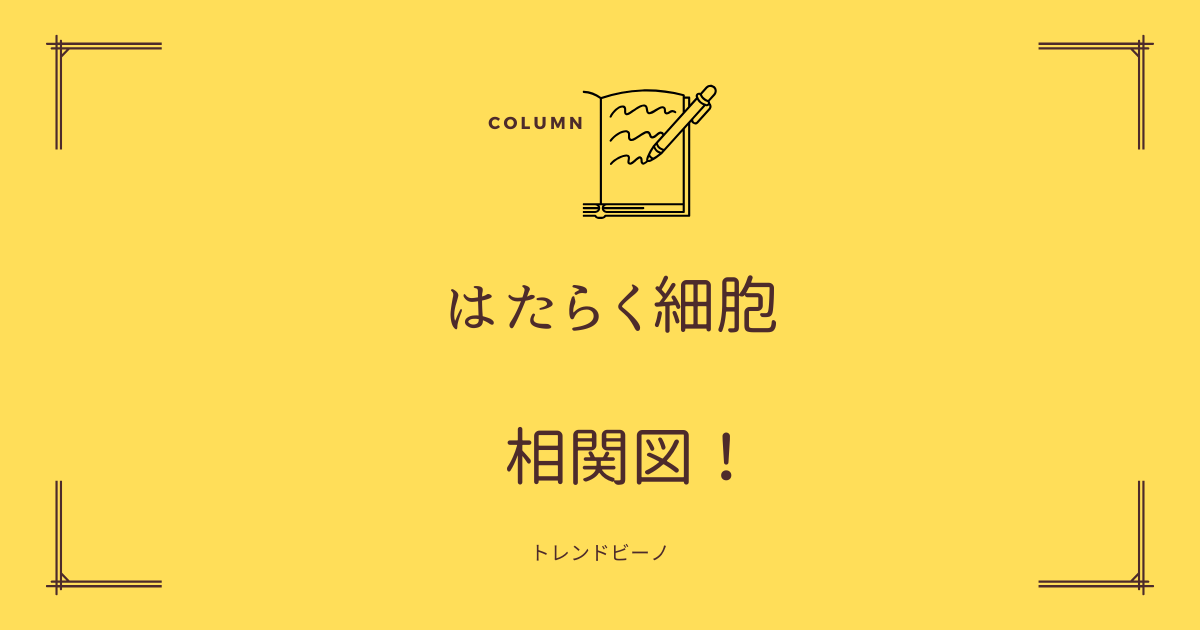
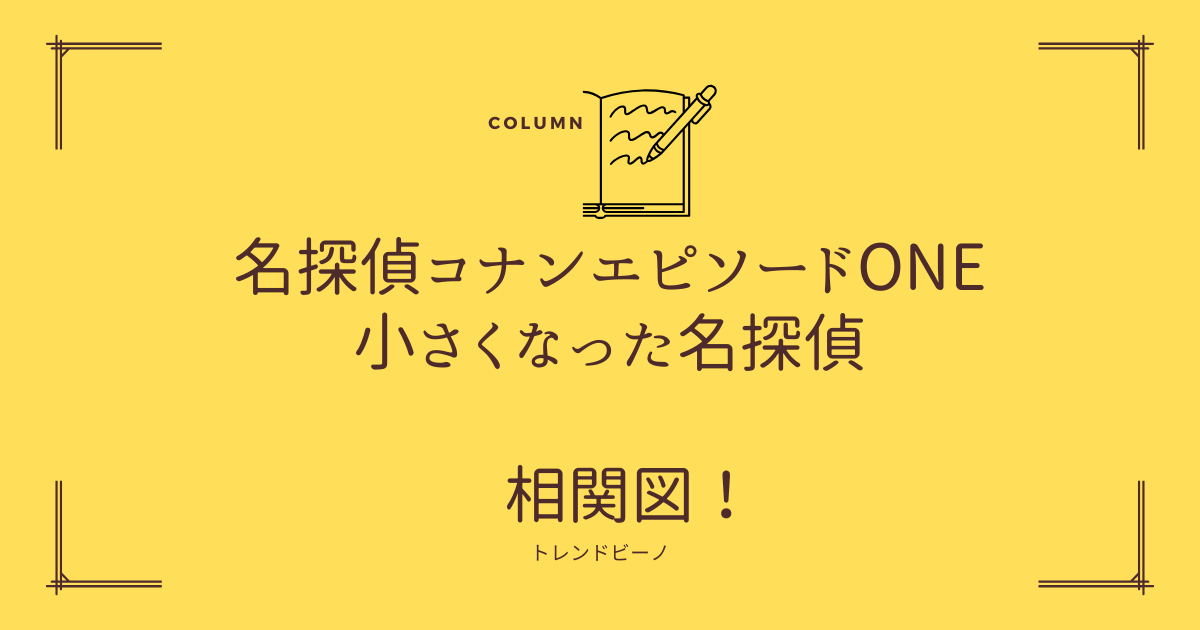

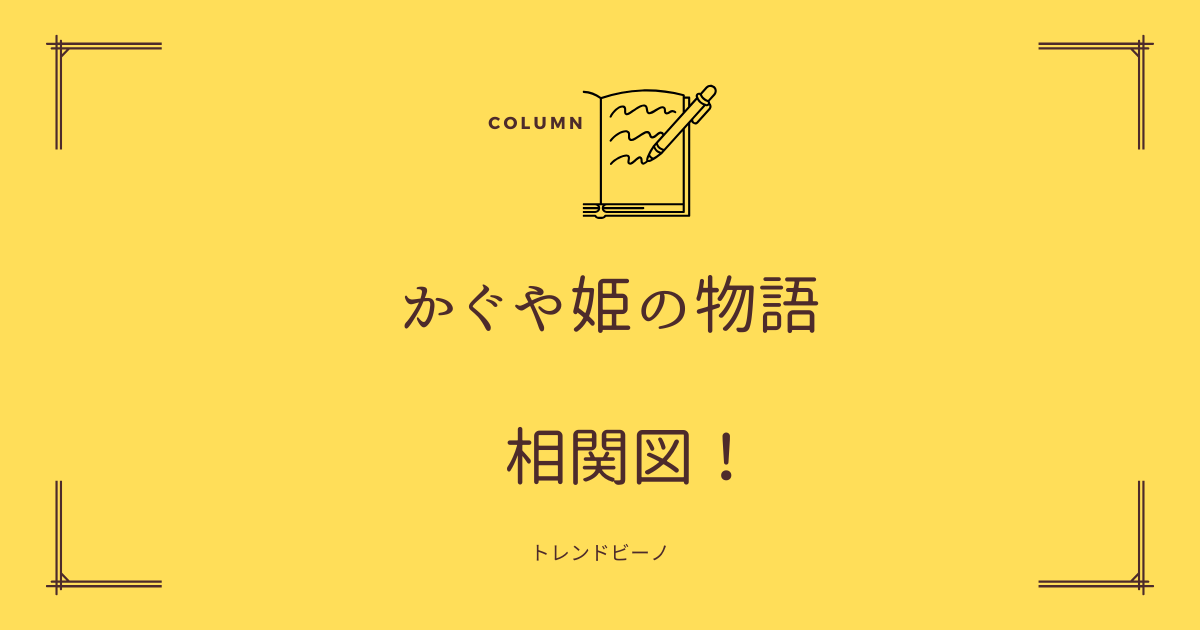
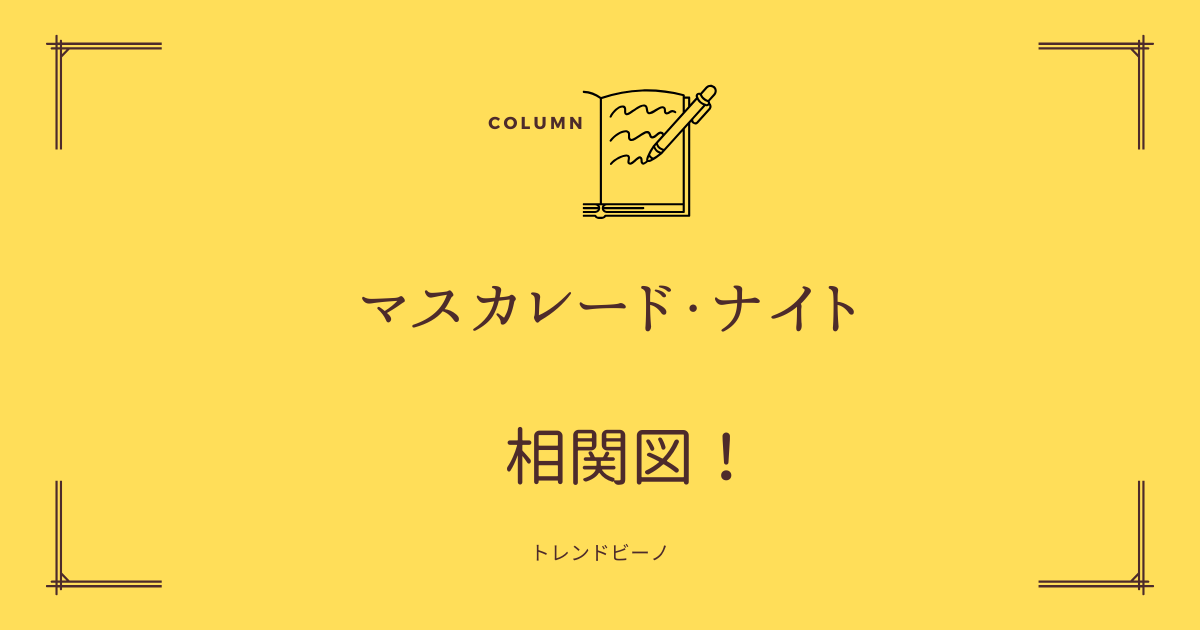
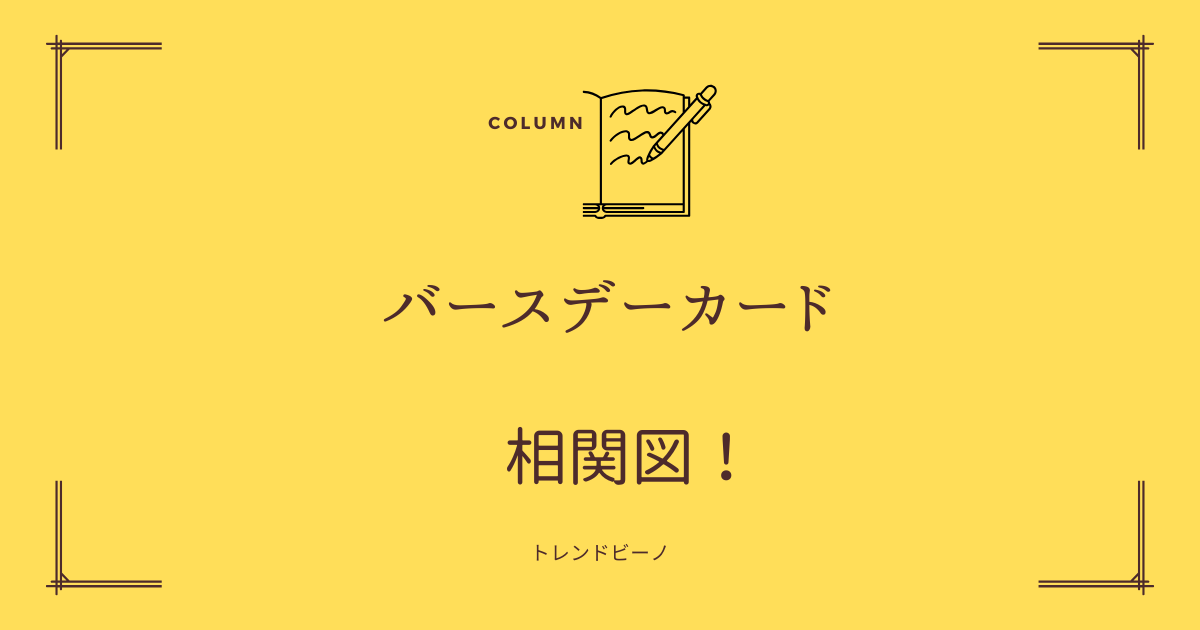
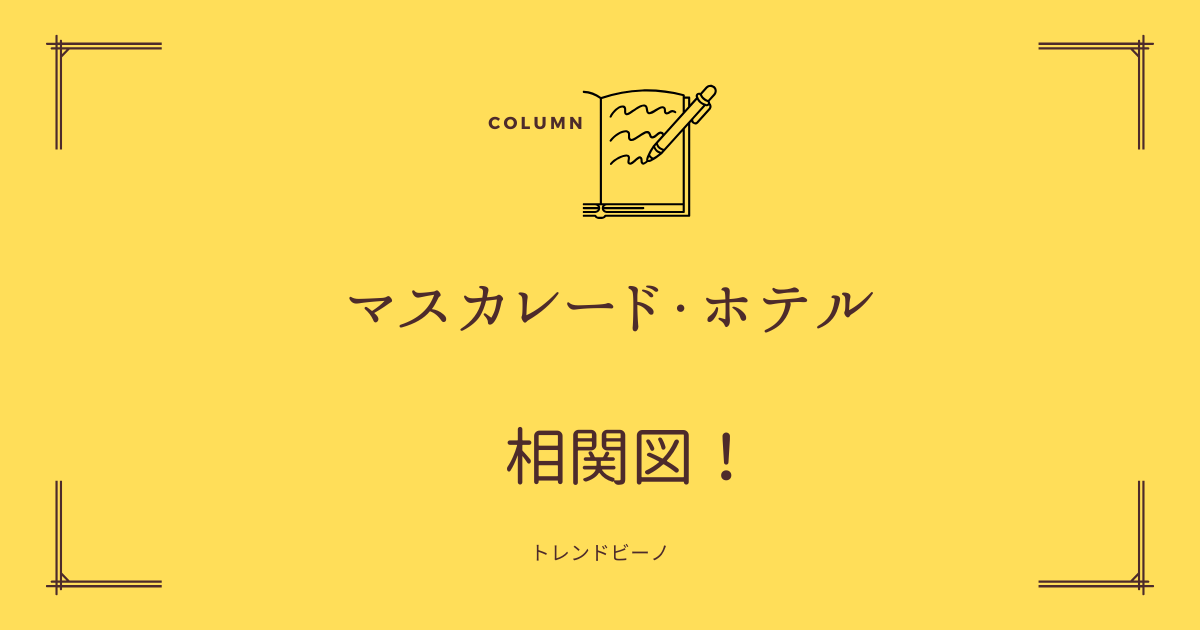
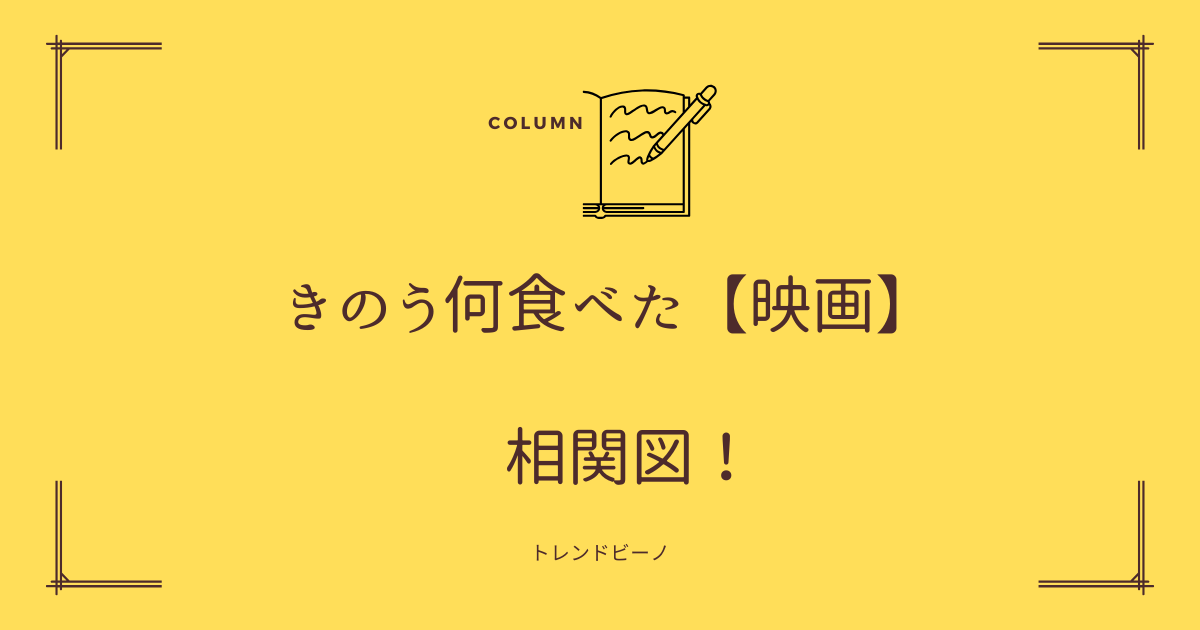
コメント