映画『君たちはどう生きるか』を見ていて、なかば頭がフリーズしそうになるのが後半の“墓のシーン”じゃないですか?
「我を学ぶものは死す」「お前、死のにおいがプンプンしているよ」そして塔の門に刻まれた「fecemi la divina potestate」って謎のラテン語…。
なんなんだこの世界観!?ってなるけど、よくよく見ていくと、これは“死”という言葉を通して描かれた“心の学び”の物語なのかも。
ということで今回は、この一見こわ〜いワードの数々を、ちょっとあたたかく、でもズバッと読み解いてみようと思います♪
「我を学ぶものは死す」とは?|“死”が意味するのは恐怖ではなく解放
まず、この「我を学ぶものは死す」って言葉、いかにも恐ろしい響きですが、これね、実は“恐怖の死”じゃないんだと思うのです。
映画の世界観には、この世の世界=執着だらけの幻想の世界っていう設定があったのかも。。と想像しています。競争して、奪って、勝ち取って…そんな価値観に染まって生きてる世界。それを“生”とみなすなら、逆にそれを手放した状態――つまり「執着を捨てて、平安を選んだ」人のことは、“死んだもの”と呼ばれてしまうのかもしれません。
でもそれって本当は、“死”じゃなくて“解放”と呼べるのかもしれません。「私はもう、この争いの世界とは距離を置きます」っていう心の選択。
それが「死す」って表現されてるだけではないのかなと感じるのです。本当は、そこからこそ“本当の命”が始まる。ちょっと逆説的だけど、この言葉の核心はそこにあると感じました。
この“死”の表現が、眞人の精神的目覚めの始まりであるという視点はこちら
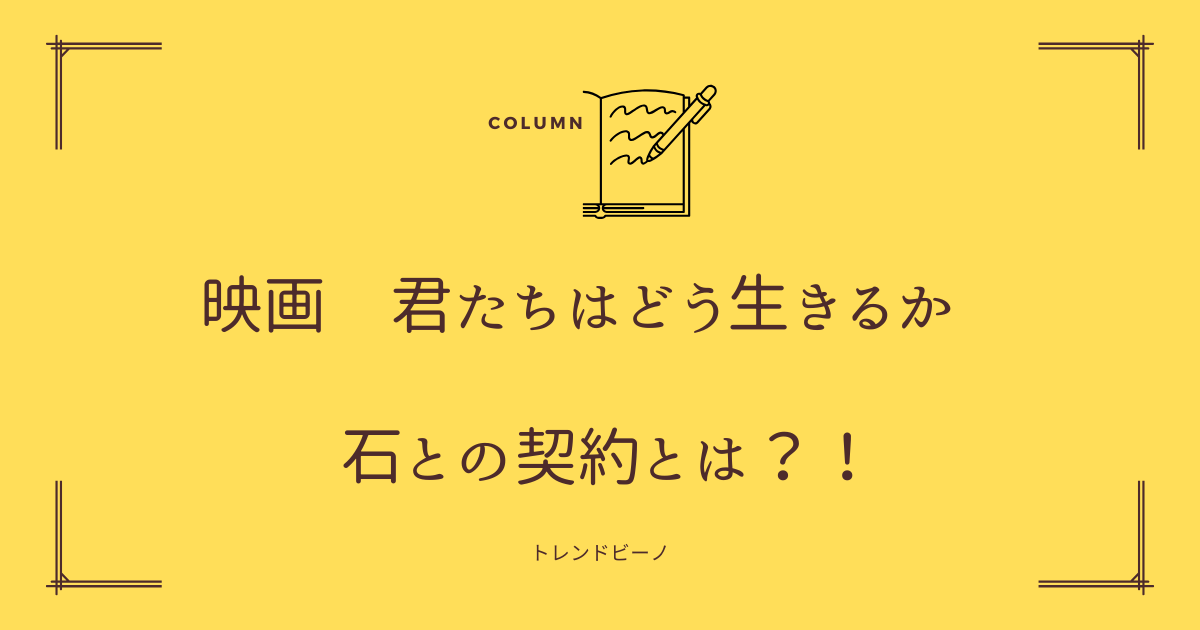
墓の主は誰?|“与えるだけ”の存在が象徴する神のような平安
で、気になるのがこの“墓”。なんか禍々しい感じするけど、キリコさんはここで手を合わせて静かに祈ってたし、ペリカンたちも門をくぐろうとしてたんですよね。
墓の主って誰なの?ってなるけど、私はここ、“神”のような存在を描いた場所だったと思うんです。奪わず、裁かず、ただ“与えるだけ”の存在。慈しみと平安に満ちた世界。
門の向こうに広がっていたのは、ただの草原。これを「退屈」と見るか、「静けさ」と受け取るかは、まさに“その人の心の状態次第”といえるのではないでしょうか。
執着を手放した心には、あの場所はきっと“天国”のように感じられる。でも、欲を手放せないままでは、その平安が逆に“恐ろしいもの”に見えるのかも。
だから、あの門は誰にでも開かれているようでいて、心の準備ができたものにしか入れない場所だったのかもしれません。
キリコの問いと眞人の答えの意味|なぜ“死のにおい”がすると言われたのか
「お前、名は?」「眞人」「ああ、まことの人か。どうりで死のにおいがプンプンしてるわけだ」キリコ婆さんのこのセリフ、ちょっと衝撃ですよね(笑)。でもこれ、ちゃんと意味がありそうに感じます。
“眞人=真の人”は、心の中の執着を手放して、平安を選ぼうとする者。つまりこの世界(=執着の世界)から見ると、「そんなやつ、生きてないのと同じ!」ってことになるのかも。
争いを手放し、優しさや与える心を選ぶ人って、争いのルールにどっぷり浸かってる人から見たら、ちょっと浮いて見えるかもしれません。
だから眞人のような存在は、キリコのように“もう知っている人”から見ると、「お、来たね。この世界を抜け出す者が」って分かるのかもしれませんね。
塔の門に刻まれたラテン語「fecemi la divina potestate」の意味とは?
塔の入り口に刻まれていたラテン語、「フェチェミ・ラ・ディヴィーナ・ポテスターテ」。なんだか古めかしいけど、これ実はダンテの『神曲』地獄篇でも見られる言葉なんだそうです。。
意味は――「神の力によって我は造られた」
『神曲』では地獄の門にこの言葉が書かれていて、そこに入る者に対して「ここではすべての希望を捨てよ」と告げていたんですって。
ただ、映画の中では“地獄”というより、**“この執着の世界の終わり”**を示すような使われ方だったのではないでしょうか。
つまり、ここから先に進む者は、もう欲や争いを抱いたままではいけない。すべてを手放して“真の静けさ”の中へ――という“心の門”として描かれていたんじゃないでしょうか。
このセリフがあるだけで、ぐっとスピリチュアルで重厚な雰囲気になりますよねえ…。
黄金の門の向こうにあったもの|“退屈”と“平安”を分ける心の視点
黄金の門をくぐった先に広がっていたのは、ただの緑が地面いっぱいに広がった広場でしたよね。え?これだけ?って思った人もいたかもしれないけど、あれこそがこの映画の象徴的、大叔父も含め、皆が心の中で求めた空間だったと思うんです。
キリコが祈り、ペリカンがなんだかわからないけども殺到しようとしたその場所。人によっては「なにもない」「退屈すぎる」と感じてしまうけど、執着を捨ててきた者には、そこが“最高の安らぎ”になるんじゃないかなと思うんです。
疲れ切ったペリカンたちはその門に意図せずとも惹かれたのかもしれません。でも彼らはまだ“奪うこと”や“競うこと”をやめられなかった。だからこそ、その穏やかに緑の地に入ることは許されなかったんじゃないでしょうか。
心がどこを向いているかで、同じ場所が“楽園”にも“虚無”にも見える。
この草原は、そんな“心の鏡”のような場所だったのかもしれません。
この草原の先に“母=ヒミ”と再会する意味と、母性とのつながりはこちら
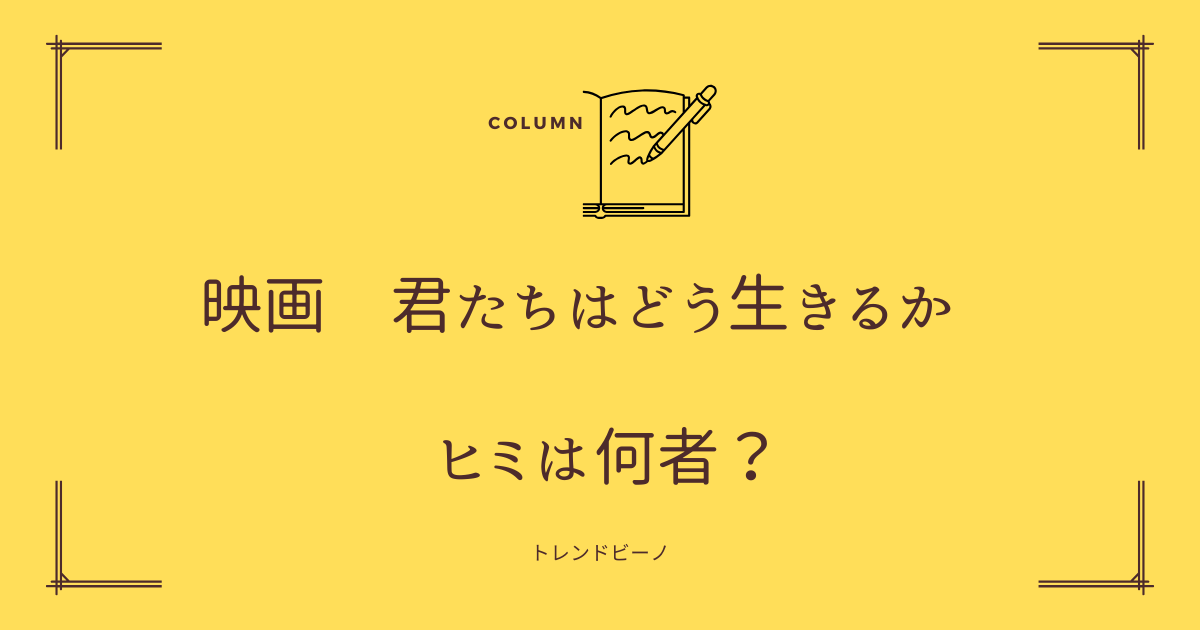
まとめ|“死”とは心の終わりではなく、執着からの目覚め
「死のにおい」「墓の主」「学ぶ者は死す」…この映画の中で繰り返し描かれた“死”というテーマは、私たちが普段抱いている恐怖とはまったく別物なのではないかと感じました。
むしろそれは、“心の生まれ変わり”。執着を手放し、本当の意味で人を赦し、愛し、穏やかに生きていこうとする人にとっては、向こうではそう呼ばれている“死”というものこそが“目覚め”だったと言えるのかもしれません。
この映画、とにかく難解だけど…「このシーン、もう一度見返してみて!」って何度でも言いたくなるほど、深いメッセージにあふれていましたね。
今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。

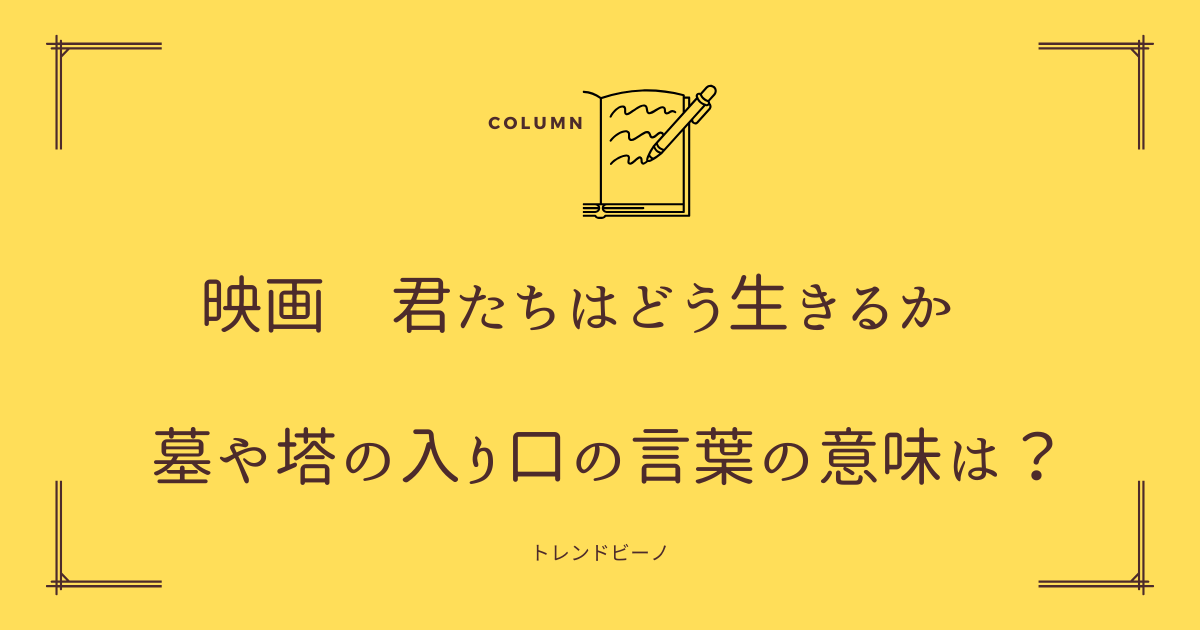
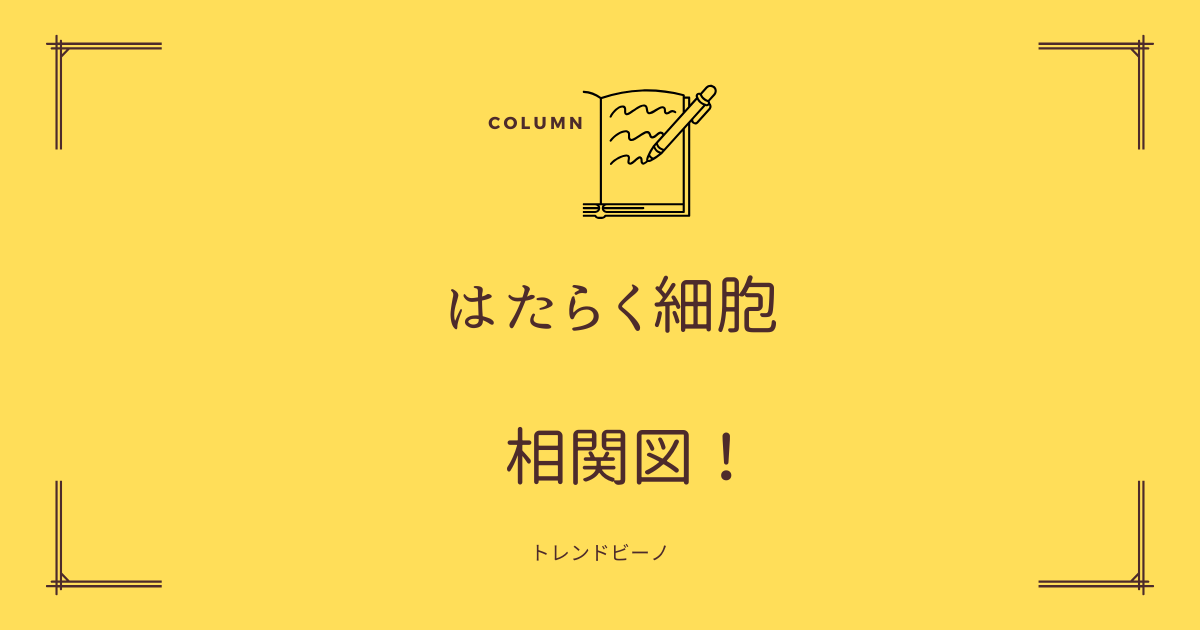
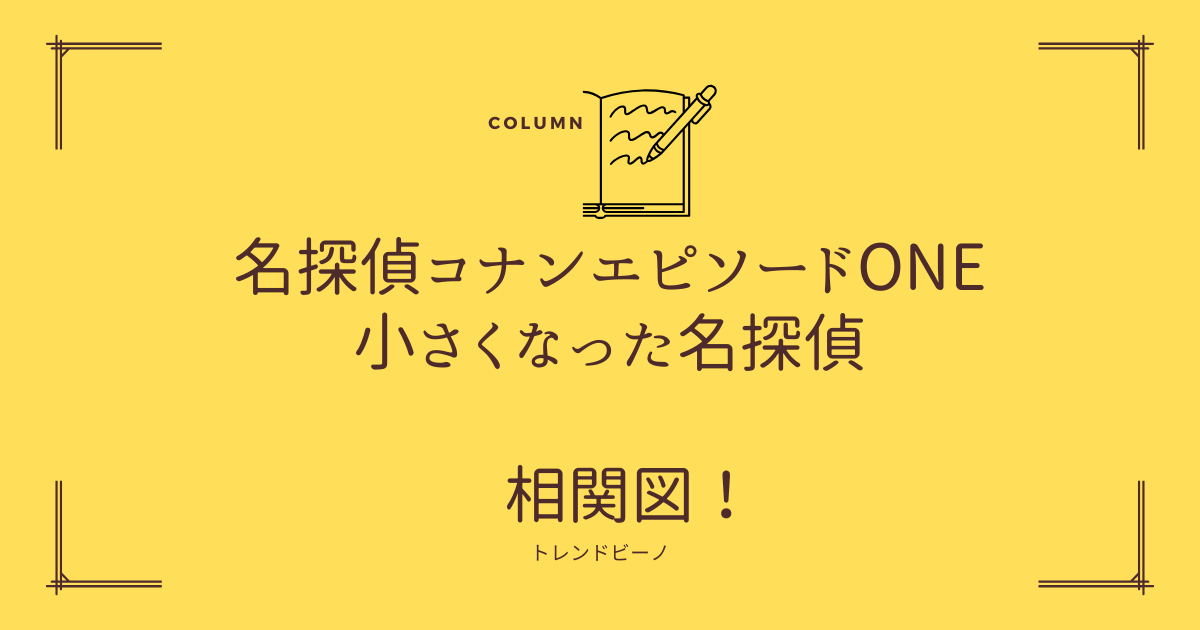

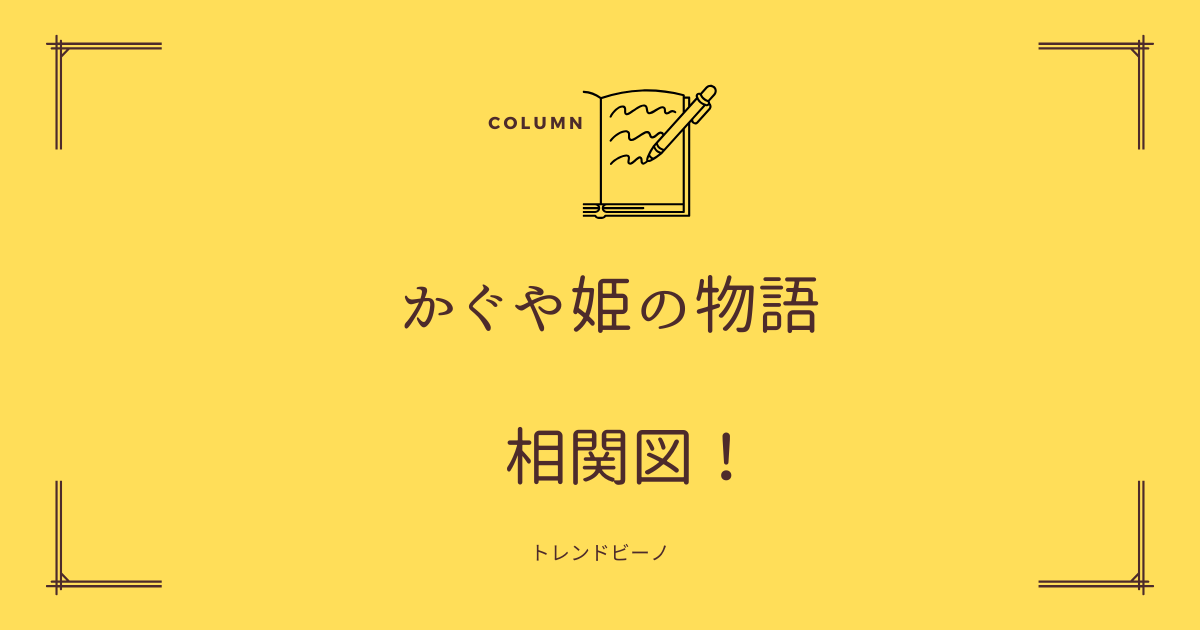
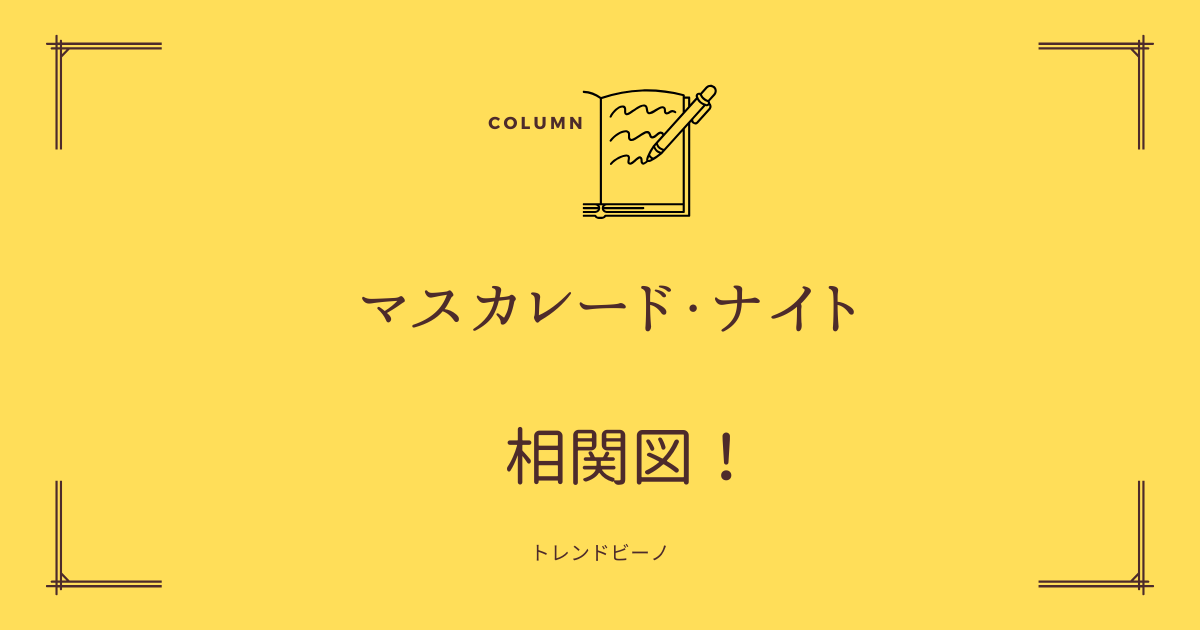
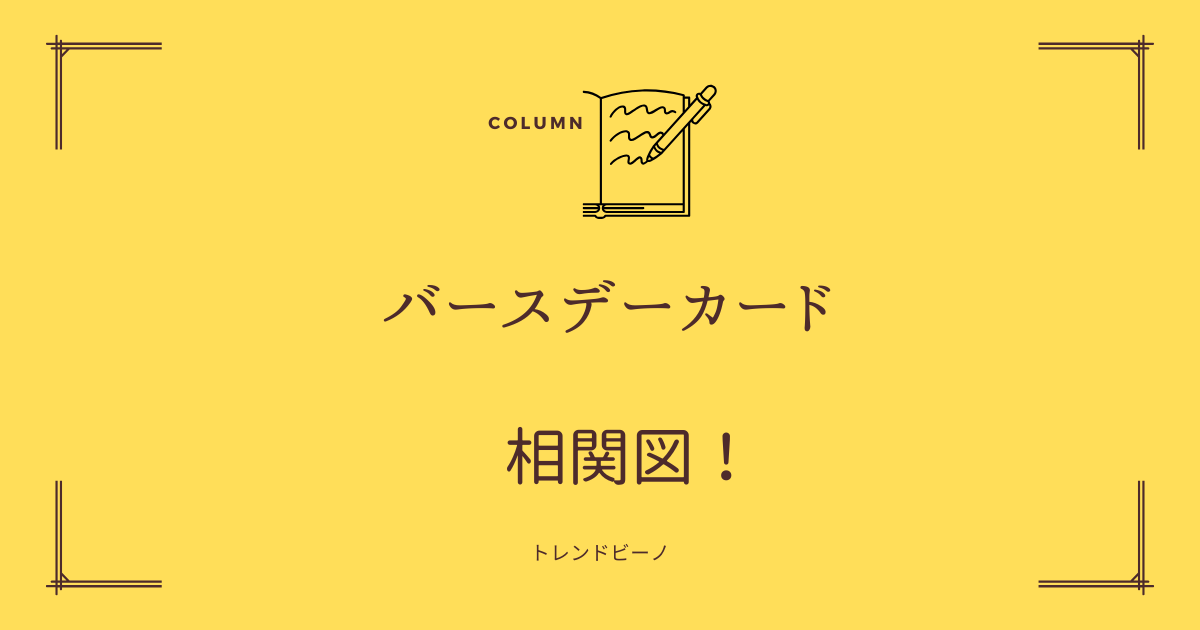
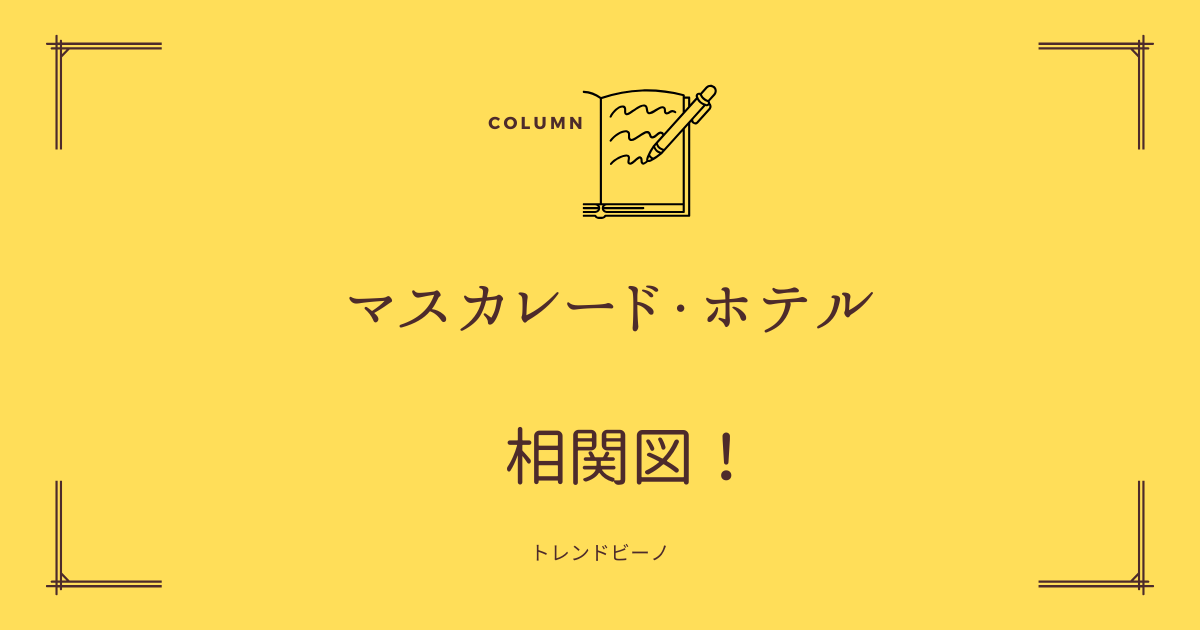
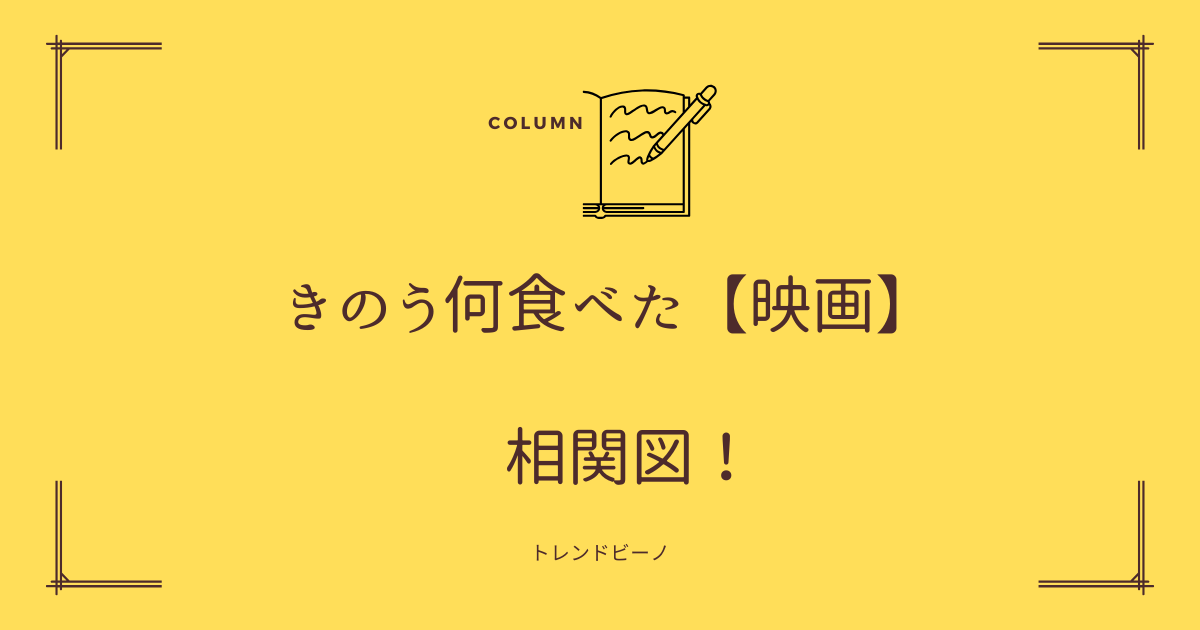
コメント