「ポルコって、あんなに男前なのに、なんで豚の姿なの?」早く人間の姿に戻ってほしい!映画を見た人の中には、こんな願いを持った人も多かったかもしれませんね。
でも、ポルコ自身はそのことをまったく気にしていない様子。むしろ、周囲の人たち──ジーナやフィオ、カーチスまでもが、「ポルコは人間に戻れるのかしら」と勝手に気にしている様子。
今回はこの“豚の姿”の意味を、信じるという行為や、周囲の視点の魔法というキーワードとともに深掘りしてみます。
ポルコが豚になった理由は?

「豚の姿=罰や呪い、或いは罪悪感」とか、ほかの映画ではよくみる設定かもしれませんね。でも、ポルコ自身はそんなふうに感じている素振りは一度も見せていないように感じるんです。
むしろ彼は、自分を豚として特別に認識しているようにも見えない。人に指摘されても、どこか「それがどうした」と言わんばかりの反応を見せるだけで、自分の見た目について悩んでいる様子もなさそうです。
逆に、周囲の人たちの方が「ポルコが人間に戻れるか」を気にしている。これは、“自分たちの価値観”から見たポルコの姿を「残念な変化」と見ているだけのように感じるんですよね。
戦争の中で国家や名誉のために動くのが当たり前の時代に、荒れた海で敵兵を助けるという“人としての道理”に従ったり、「誰にも従わず、自分の心に正直に生きる」という選択をしたポルコ。
それは彼の“自由への意志”の表れであり、むしろ悪い意味で人間っぽい自我や欲望から解放された、ある種の進化とも言える姿なのかなと思ったりします。
でも、その”進化”は、周囲の人間には“理解不能”だった。だから彼は、彼らにとって“価値のないもの”──この映画の中ではそれを「豚」の姿に象徴させたのかなと推察しています。実は、魔法(?)にかけられていたのは、ポルコ自身ではなく、周囲の人々だったのかもしれません。
ポルコ(マルコ)が人間の顔に時折戻る理由は?
映画の中でポルコが人間の姿に戻ったように見える場面は、2つあります。ひとつは、銃弾を整備しているとき。もうひとつは、フィオに唇へキスをされた瞬間。
これらの共通点は、「ポルコの中に、名誉や欲という“人間的な感情”が芽生えたタイミング」だということ。銃弾を整備する場面では、カーチスとの再戦に向けて「名誉を取り戻す」という気持ちがあった。そしてキスの瞬間は、フィオへの心の揺らぎがピークに達した場面。
つまり、ポルコが人間の顔に戻ったのは、彼が“いわゆる人間の感情”に呑まれたとき。逆に言えば、ふだんのポルコは、もっと純粋で自由で、誰にも支配されない“理想の豚(存在)”だったということ。周囲から見れば「ポルコが戻ってきた」と思える瞬間は、実はポルコの“気が迷った瞬間”だったのかもしれません。
ポルコの顔が豚なのは魔法のせい?
魔法のように見えて、実は“魔法にかかっていたのは周囲の人間”だった──というのが今回の管理人の視点。ポルコ自身はなにも変わっていない。
人間としての外見を捨てたわけでもなく、社会や価値観から距離を置き、“誰にも縛られない自由な存在”としての在り方を選んでいただけ。
戦争中に敵兵を助けたポルコ。それは“信じる”という行為の象徴だった。「困っている人を助ける」という人間としての道理を信じた結果、国からは裏切り者として追われた。信じたことに裏切られ、正しいと思ったことが否定された──それが、彼が“信じる”という言葉を嫌う理由にもつながったのではないでしょうか。
でも、その中でなお、自分の信念に従って空を飛び、誰にも従わない。それは人間の枠を超えた「ポルコらしさ」であり、むしろ“豚の姿”というより“真の自由人”の象徴だったのではないでしょうか。
ポルコが信じることを嫌っていたわけは?
「信じるなんて言葉、嫌いなんだよ」──ポルコのこのセリフには、ただの照れや皮肉ではなく、過去の痛みと距離のとり方がにじんでいます。
かつてポルコは、国家を信じ、仲間を信じ、戦争の正義を信じていた。でも結果的に、それらはすべて崩れてしまった。信じることが、何も生み出さず、むしろ自分を傷つけることになった。そんな体験が、「信じる」という言葉への拒絶に変わったのかもしれません。
でも、「信じる」って本来は、誰かとのつながりの中で何かを生み出す力を持っているものだと思うんです。ポルコも本当はそれを知っていた。人はひとりでは何も生み出せない──信じる気持ちがあってこそ、誰かのために何かを届けられる。
フィオという、まっすぐで、優しくて、純粋な存在に触れたことで、ポルコの中に「また誰かを信じてもいいのかもしれない」という気持ちが静かに芽生えた。それは、希望に近いものであり、ずっと奥にしまっていた「何かを生み出したい」という思いが、ふっと浮かび上がった瞬間でもあったと思うんです。
ポルコは自由を求めて空を飛んでいたけれど、それは決して自分勝手に生きていたわけじゃない。むしろ、誰かのために飛びたい。でも、そういう気持ちにちゃんと向き合うのが難しかった。だからこそ、フィオの存在が、彼にとってどれほど意味のあるものだったかがわかります。
もしかすると、その気持ちが背中を押して、昼間のジーナの庭にふらりと立ち寄ったのかもしれません。「信じたから」ではない。「信じてもいいかもしれない」と思えるようになったから。
ジーナとの関係性や、フィオとの心の動きは、相関図で見るとさらに深く理解できますよ。
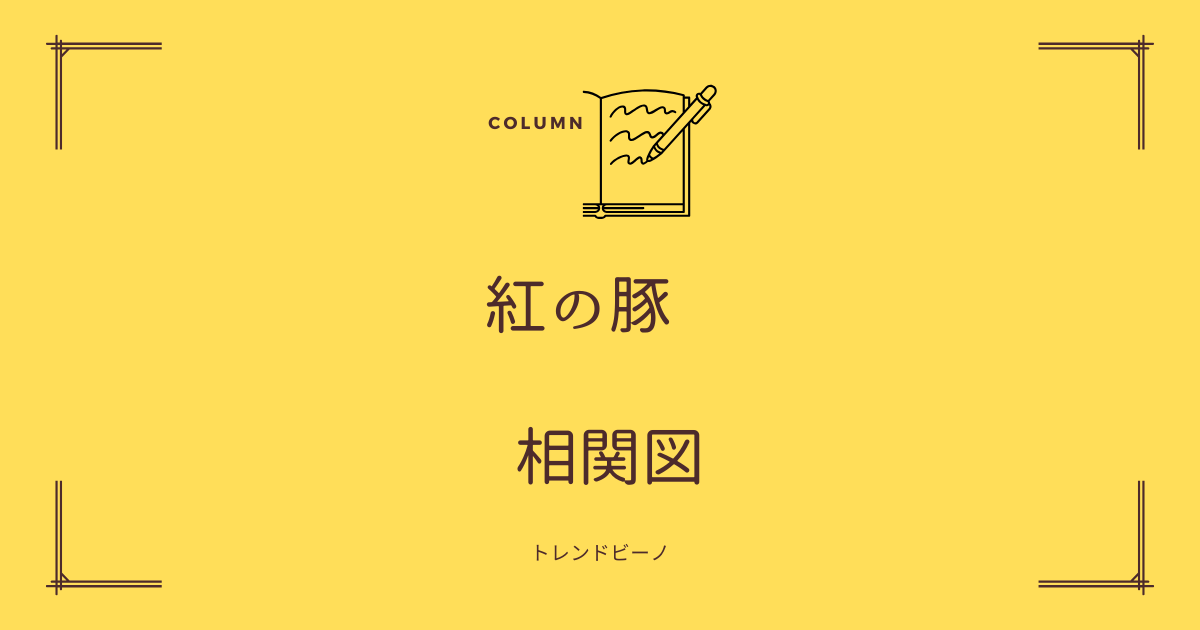
このセリフを含めた名言一覧はこちらの記事でも紹介しています
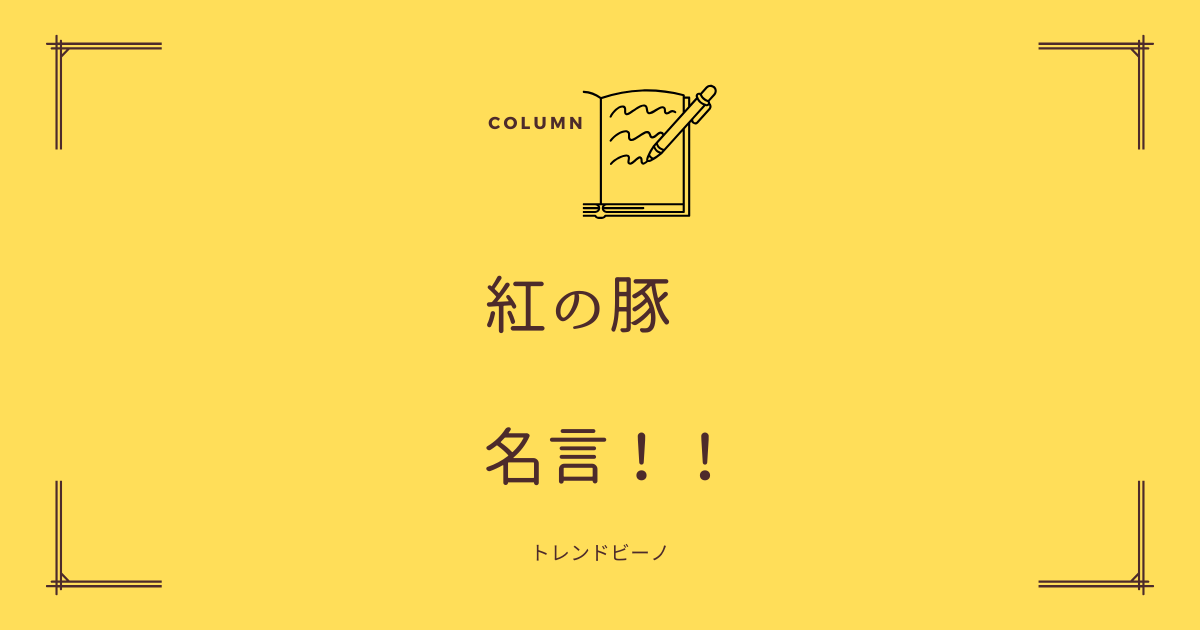
まとめ|ポルコは何も変わっていなかった。変わったのは周囲の目だった
ポルコが豚になったのではなく、周囲の人たちがそう“見てしまった”だけではないかと思いました。彼は最初から最後まで魅力的で、かっこよくて、人として誠実でした。だからこそ、ジーナもフィオも、カーチスすらも彼に惹かれた。
彼の周りの人にとっては、彼が豚の姿をしていても、心の目で見れば、そこには“本物の男”がいた。信じることを失っても、自分の信念を貫いたポルコは、普通の人がまだたどり着けていない領域にまで達した“人間”だったのかもしれないなと妄想したりしています。
今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

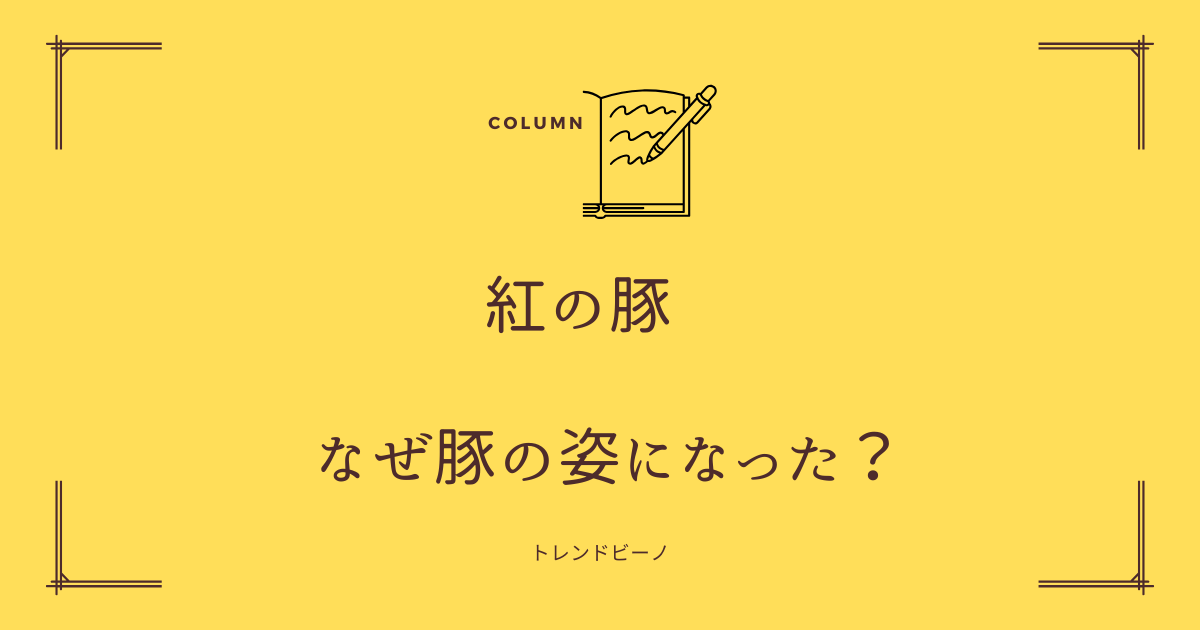
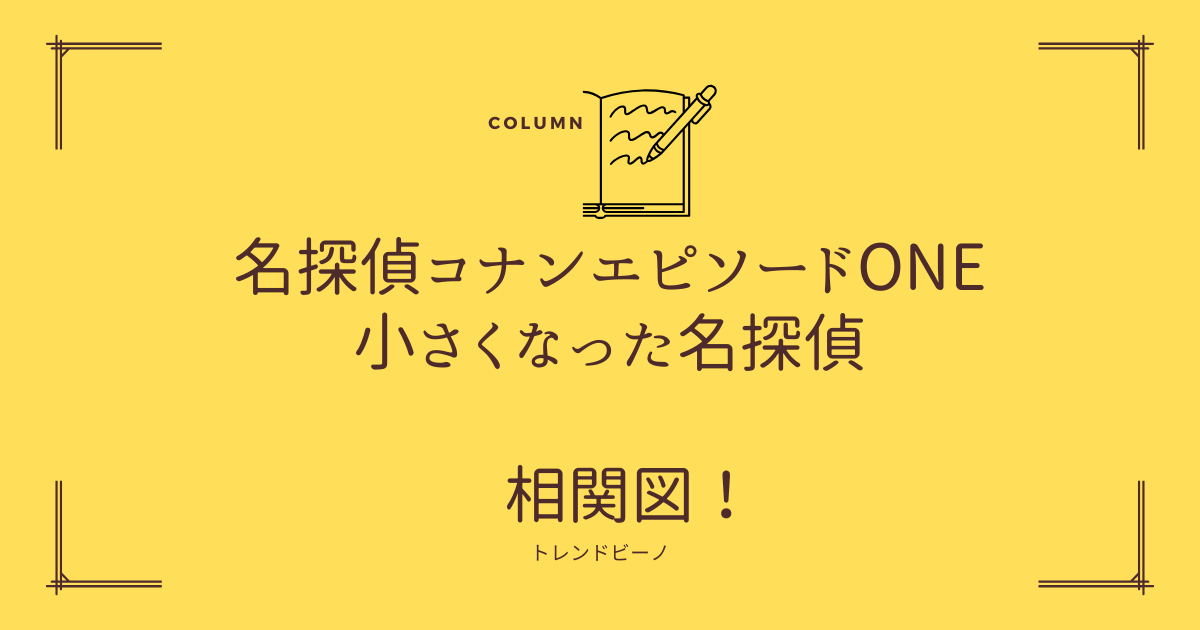

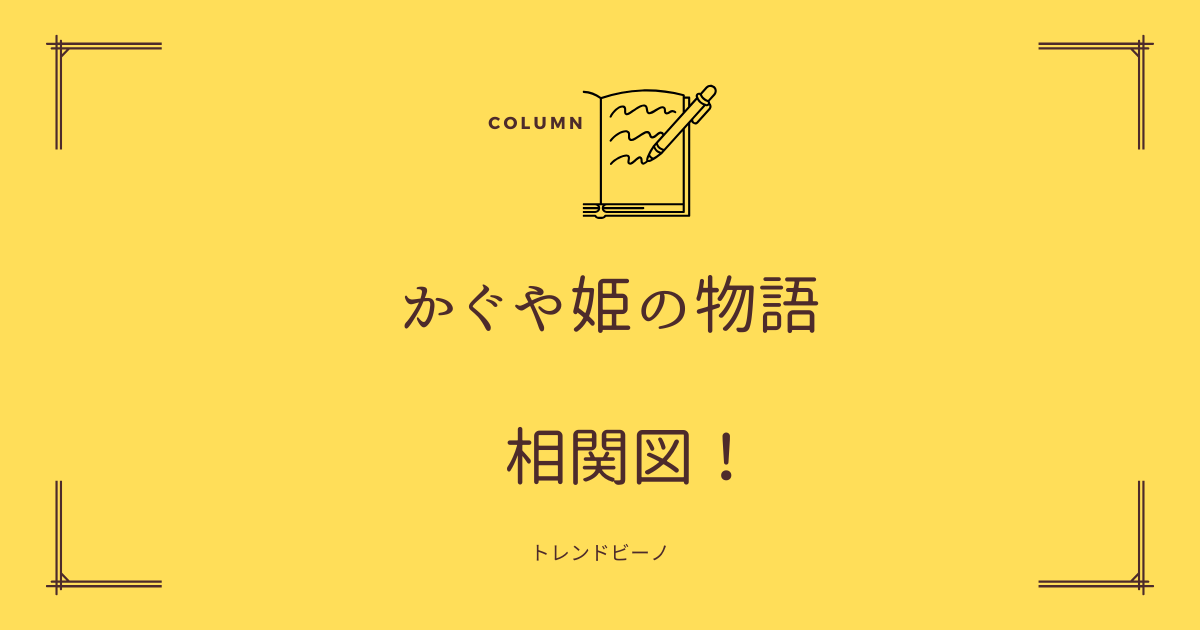
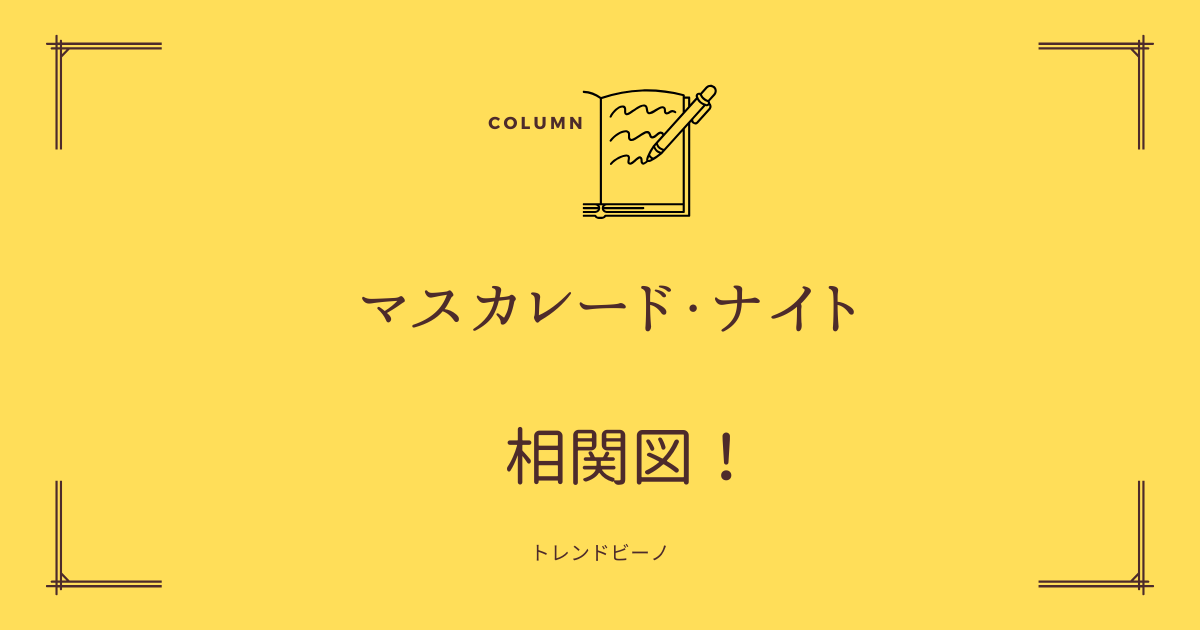
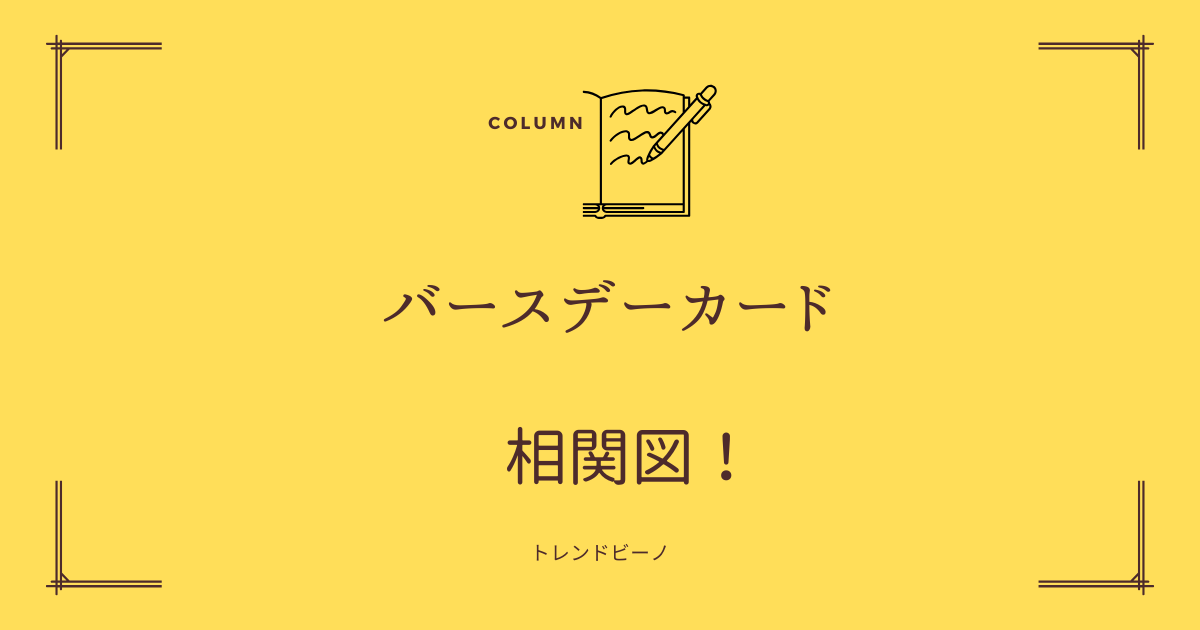
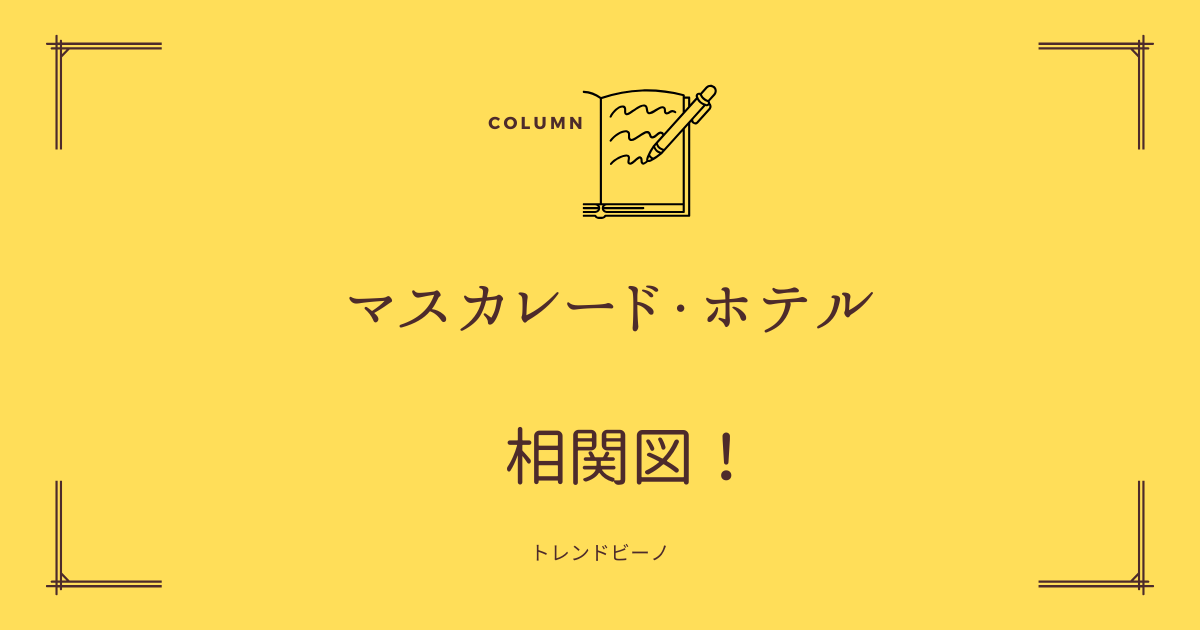
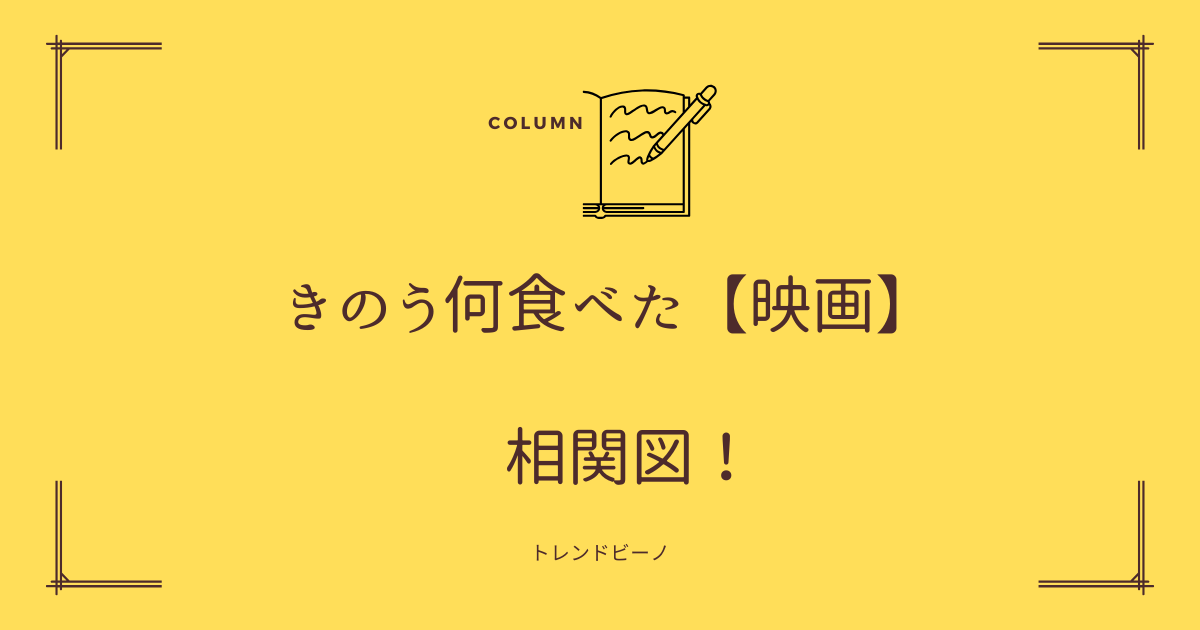
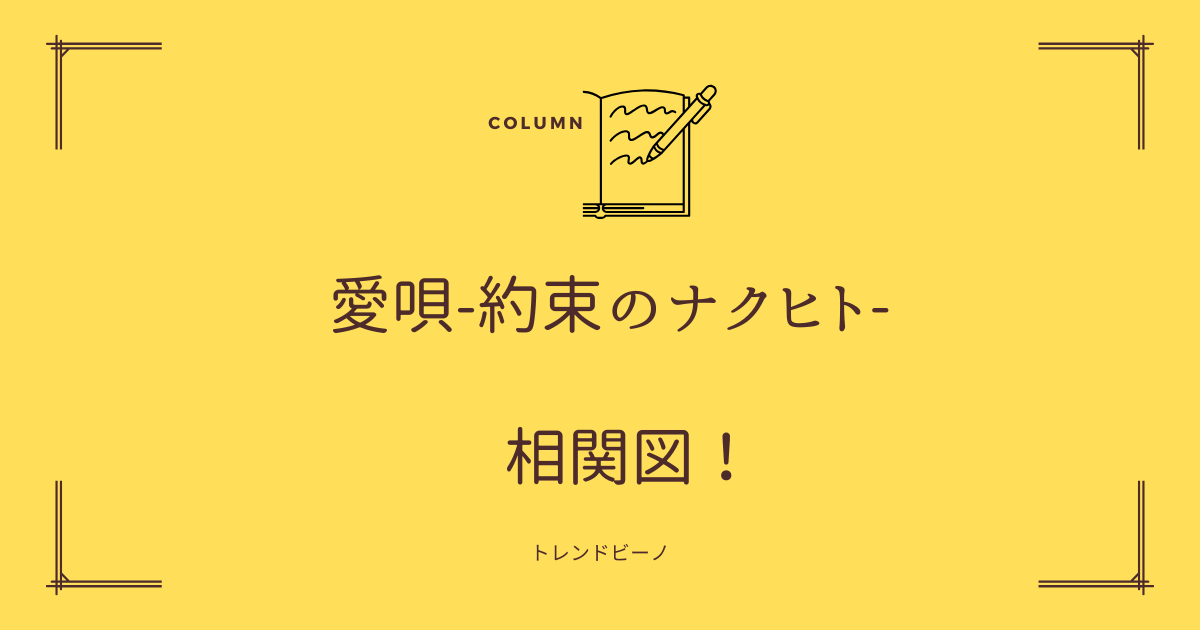
コメント