スティッチは壊すために作られた存在。誰が何をしても変わらない、“遺伝子レベルの破壊プログラム”。──そう言われていたはずなのに、なぜか彼は、少しずつ変わっていった。
特別な技術も、薬もない。ただ、そばにいたのは、リロという1人の小さな女の子。
今回は、「なぜリロにだけ、スティッチを変えることができたのか?」その秘密を、ママ風に本気で掘り下げてみます。
「あの子でも無理だよ」──スティッチの破壊プログラムは変えられない?
映画の中盤、とても象徴的なセリフがあります。
リロとスティッチの様子を見ていたジャンバが、こんな風に言うんです。「あの女の子もご苦労なこった。626(スティッチ)の破壊プログラムを変えるのは不可能だ。」
この一言、まさに“外側の論理”の象徴。スティッチは、ジャンバ博士が設計した「破壊するためだけに作られた存在」。知性も、力も、反射神経も、すべてが“破壊”に最適化された遺伝子レベルの兵器。それを「プログラム」と言い切るのも無理はない。
だから「変わる」ことなんてありえない。「心が動く」ことすら想定されていない。そんな風に“機械のような存在”として、彼は定義されていたんです。
でも、その“絶対無理”の定義を、リロはひっくり返すんですよね。
しかも、特別な薬や技術を使ったわけじゃない。ただ、スティッチの隣に座って、話しかけて、一緒に眠って、家族だって言っただけ。
これって、ほんとにすごいよね。いや、もちろん物語っていうのはわかってますよ(笑)。でも、実際に似たようなことが起こりそうな気がして、で、それを5歳の女の子がやっちゃうんだから。
だって、世界が「プログラムだから変えられない」と見放した存在を、「でも、ここにいていいよ」と受け入れただけで、その子の中の“変わる力”が芽生えたんですよ?
それはもう、文字通り「不可能を可能にした」というやつですよね。じゃあ──なぜ、リロにはそれができたのか?
リロが“変えようとしなかった”から変わったというパラドックス
世の中の大人たちは、何かを「変える」とき、まず「直そう」とするのよね。悪いところを指摘して、押さえつけて、理屈で教えて、矯正していく。たしかにそれが必要な場面もあるけど、スティッチには効かなかった。というか、それをすればするほど、彼は暴れた。
でも、リロは違った。彼女はスティッチを「変えよう」としなかった。「なにかがおかしい子」「やっかいな存在」として扱わなかった。
代わりに、「名前をつけて」「隣に座って」「ぬいぐるみと一緒に話して」「犬として一緒に暮らした」──それだけ。
つまり、リロは「変わらなくていい」と思って接していたのよ。でもね、そこにすごい逆説があるの。
“変えようとしない人”に出会ったとき、人は初めて「自分から変わりたい」と思えるんだよ。
それまでのスティッチは、「こうあれ」とプログラムを押しつけられてきた。だから暴れたし、それ以外のことを拒絶した。でも、リロだけは、受け入れられる範囲でスティッチを受け入れようとした。
それが、彼の中に「じゃあ、変わってみてもいいかな…」って気持ちを芽生えさせたんだよね。
このパラドックス、じつは人間関係でもよくある。変えようとすると反発される。でも、丸ごと受け入れると、自分の方から「もっとよくなりたい」と思い始める。
リロは、それを既に知ってたのかもしれない。
“壊す存在”と“壊れかけた存在”が出会った時に起きたこと
スティッチは「破壊のために生まれた」存在。でも、リロだって“壊れかけた子ども”だった。家族を突然失い、理解されず、まわりの子たちから浮いて、何をしても報われない。
魚にパンをやって、友達を呪って、ぬいぐるみに話しかけて──大人から見たら“変わった子”だったかもしれない。でも、それって、リロなりの「生きのびる手段」だったんだよね。
彼女は壊れなかった。だけど、ギリギリだった。そして、そんなリロだからこそ、スティッチを見たときに「こわくて排除すべき存在」じゃなくて、「わたしと同じだ」と感じられたんだと思うの。
自分を壊さずに守ってくれた人──それが、リロの中では「両親」だった。そして、今度は自分が“親”の側になって、スティッチを守ろうとした。
自分がしてもらったことを、今度は自分がする番。これはね、ただの「友情」とか「子どもの優しさ」とか、そんなキレイごとじゃないの。
リロの中にある、“経験を通してしか得られない痛みの理解”が、スティッチを変えていった。
プログラムを超えるのは、“ただそこにいる”という愛と、選べる自由
最後に一番大切なこと。スティッチは、どこかの瞬間で「人間的に目覚めた」わけじゃない。奇跡のようなひらめきが降ってきたんでもない。
ただ、リロがそばにいてくれて、毎日を一緒に過ごしてくれて、「ここにいていいよ」と言い続けてくれた。
──それだけ。
その“ただそばにいる”という愛の中で、リロはこんなことも言った。
「あなたって壊してばっかりなのね。たまには何か作ってみたらどう?」
これは怒りでも責めでもない、ただのやさしい提案だった。そしてスティッチは、その言葉を初めて“受け取った”。指示や命令には反抗していた彼が、自分の意思で「じゃあ、やってみようかな」と感じた瞬間。
彼は部屋の中で、サンフランシスコの街並みを一生懸命に再現した。もちろん、完成してすぐに壊してしまうんだけど──でも、それでも大きな一歩だった。
リロは、「壊すしかない」と思い込んでいた彼に、「創造するという別のスイッチもあるよ」と教えた。しかも、「どちらを選ぶかは、あなたの自由」だと。
スティッチは、“エゴの破壊スイッチ”しか持っていなかった子だった。でも、リロが見せたのは、「創ることもできる」というもうひとつの選択肢。
それを選んだとき、もしかすると彼の中の寂しさが、ほんの少し薄れていったのかもしれない。だから、彼はだんだんと「創る」という行動を選ぶようになった。
それは、“変えられた”のではなく、“自分で選んだ”からこそ価値があったんだと思う。この世界には、“壊すこと”を止められない人もいる。
でも、“壊したいほど孤独な心”を、そっと隣に座って受け止めてくれる人がいたら──その人のプログラムは、きっと書き換わっていく。リロはその「そばにいる力」と「選ばせる自由」を、無意識に信じていたんじゃないかな。
そしてそれこそが、この物語のいちばん深い「家族の力」だったんだと思う。
まとめ|「変えようとしなかった」リロが起こした、心の奇跡
スティッチは壊すために作られた存在。誰もが「変えられない」と思った相手に対して、リロは“変えようとしなかった”。
ただ隣に座って、名前を呼んで、一緒に過ごした。その「変えないという愛」が、スティッチに「自分で変わってみたい」と思わせたんです。
壊すしかなかった存在が、「作ってみよう」と思えた。それは、命令じゃなく、“選べる自由”をくれた家族の力。
リロのやさしさは、奇跡じゃなくて、“そばにいる”という毎日の積み重ね。だからこそ、プログラムさえも超えて、スティッチの心を動かしたんだと思います。
今日も最後までご覧いただいて、ありがとうございます。

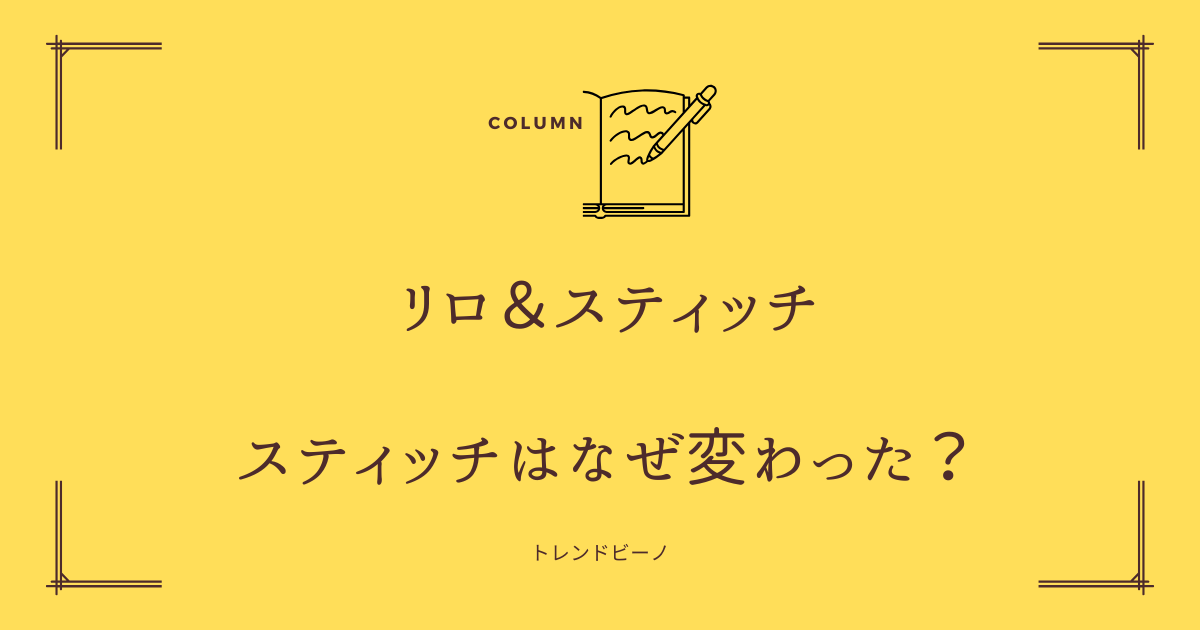
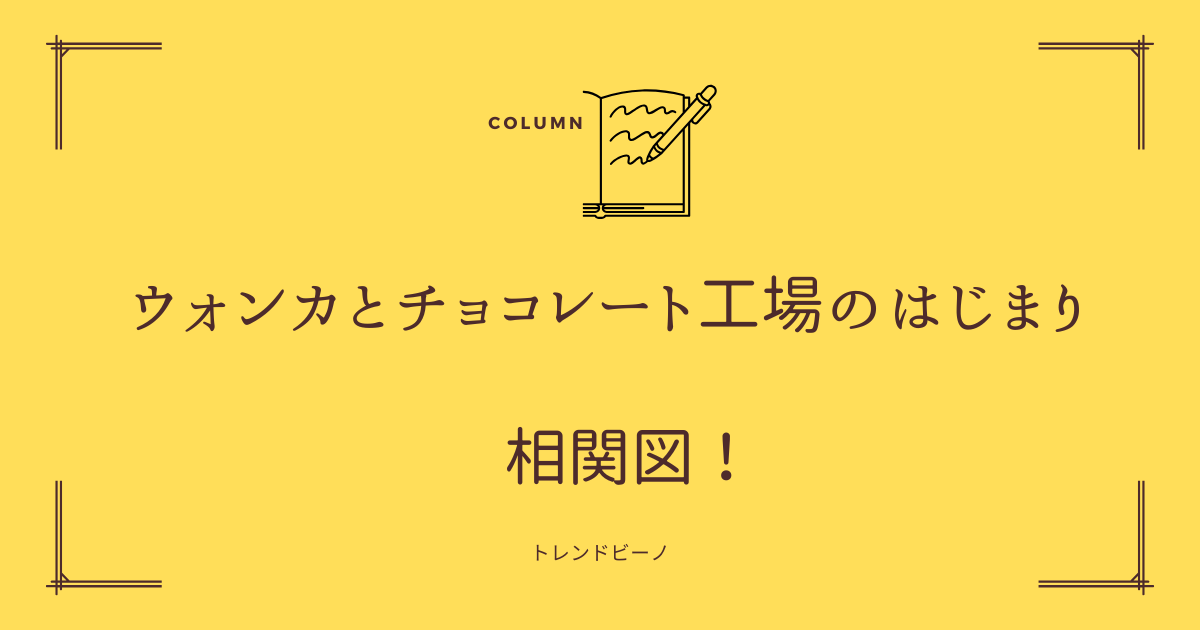
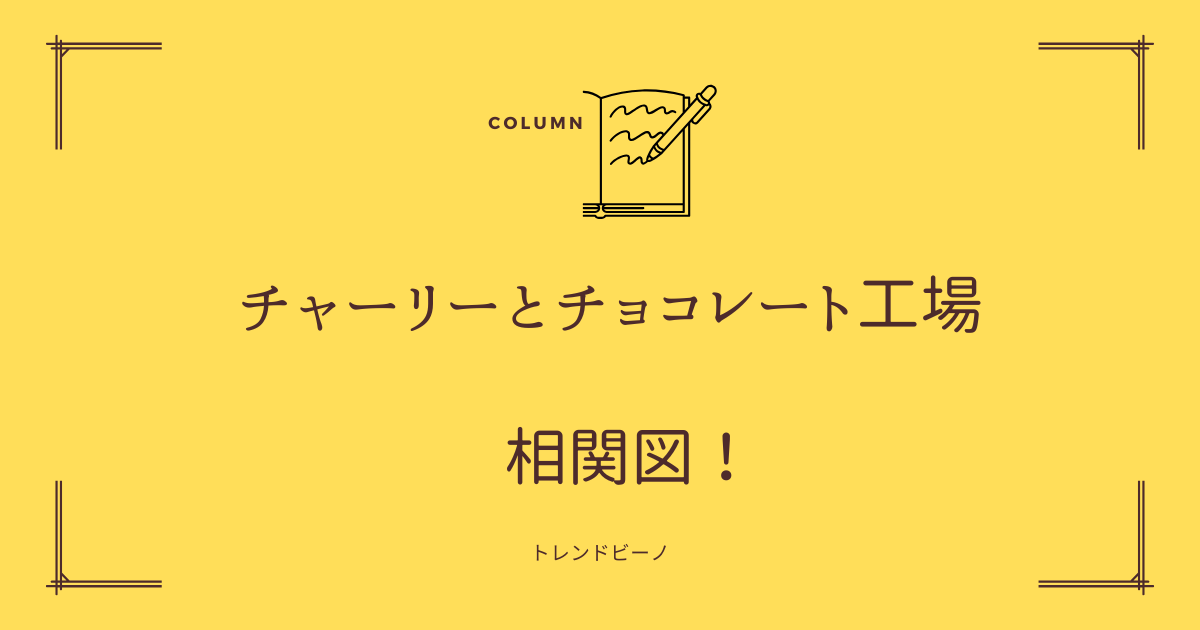
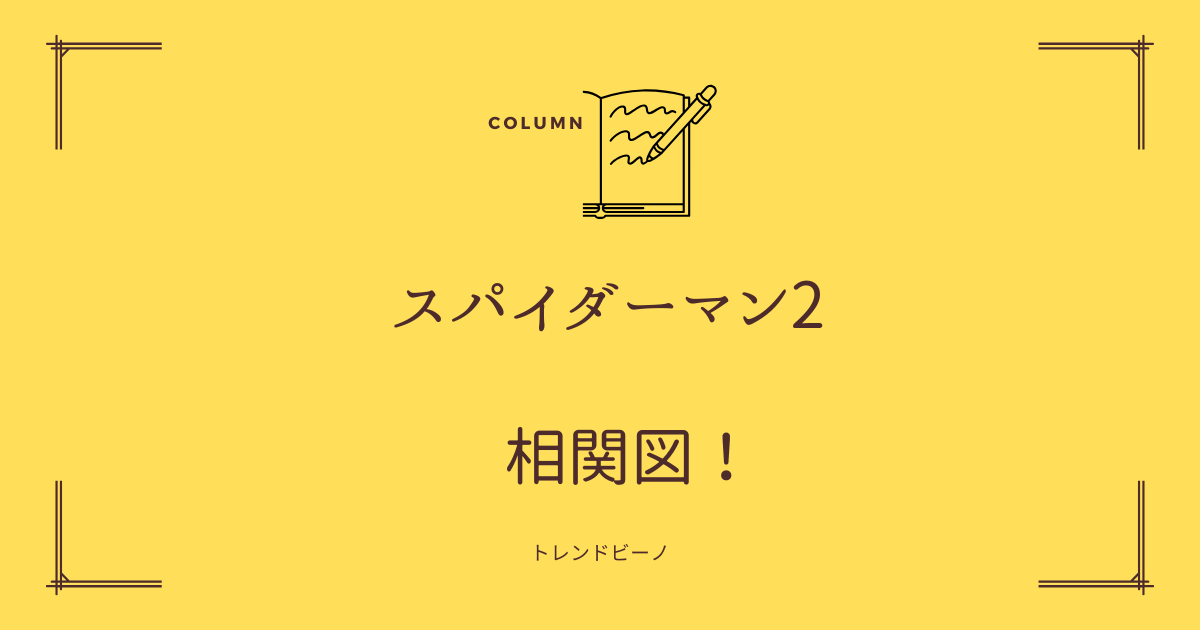
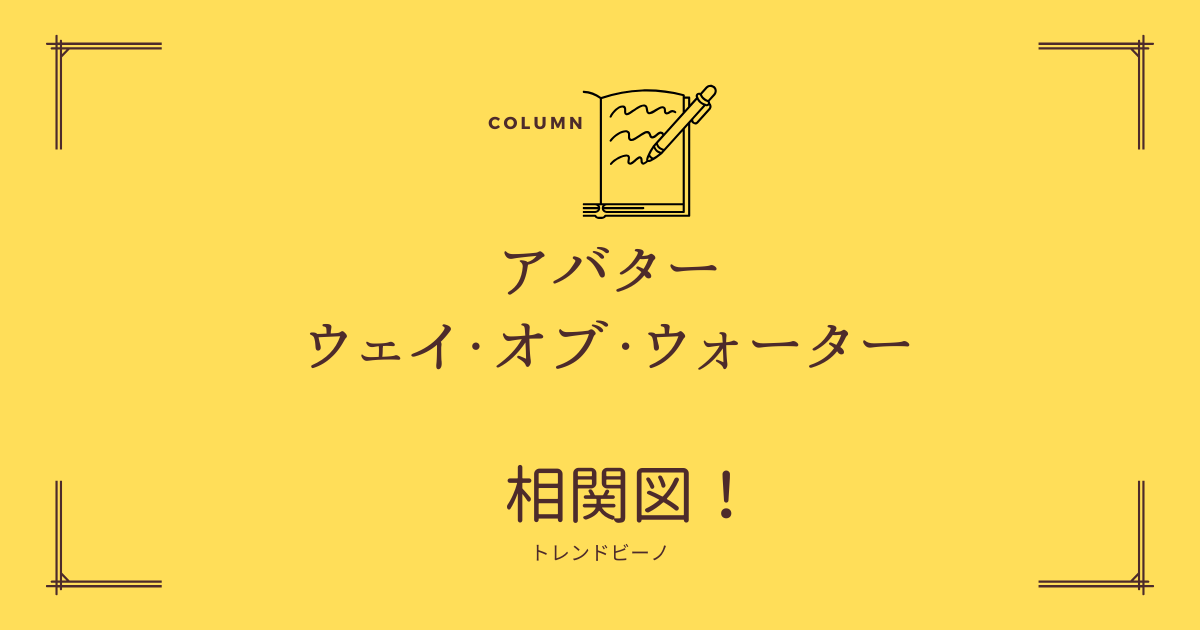
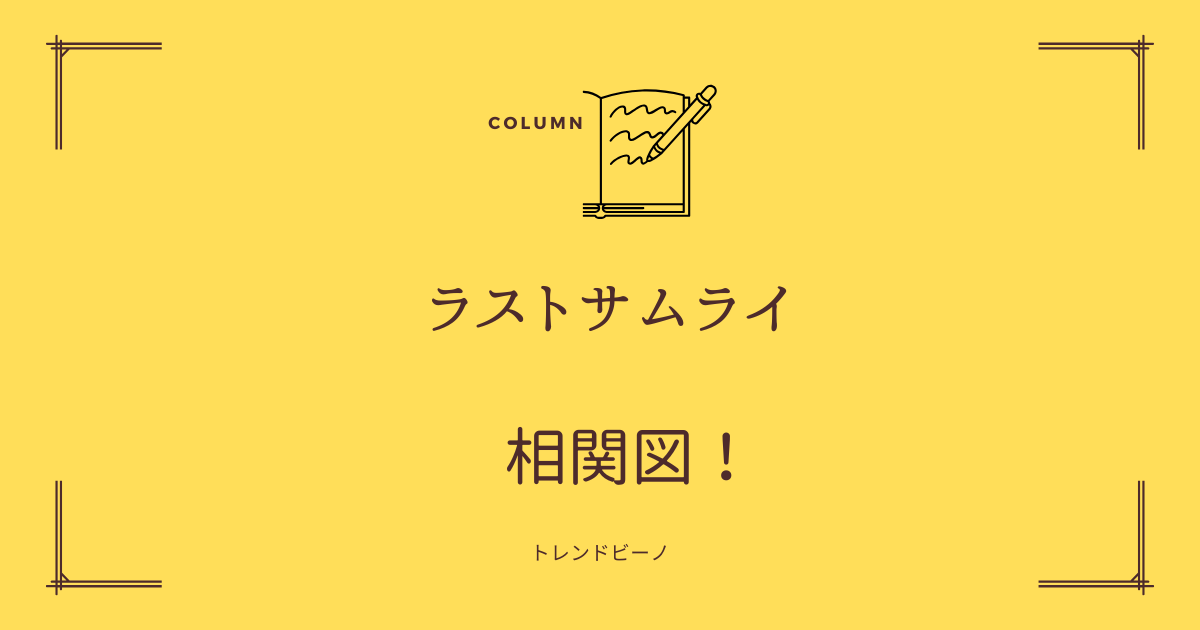
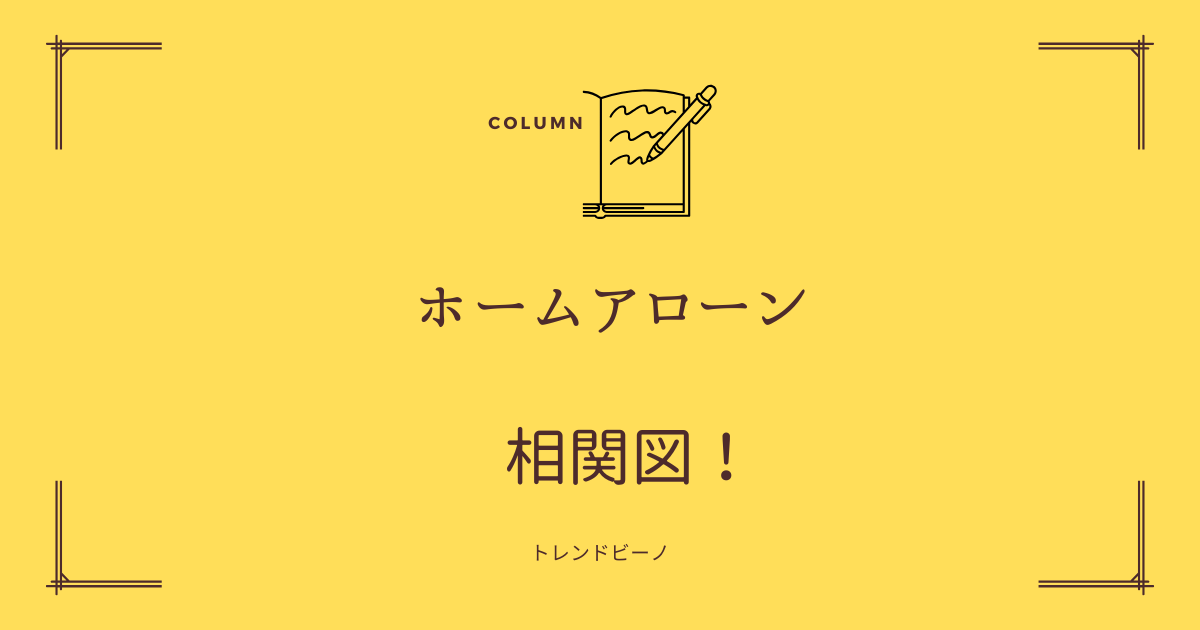
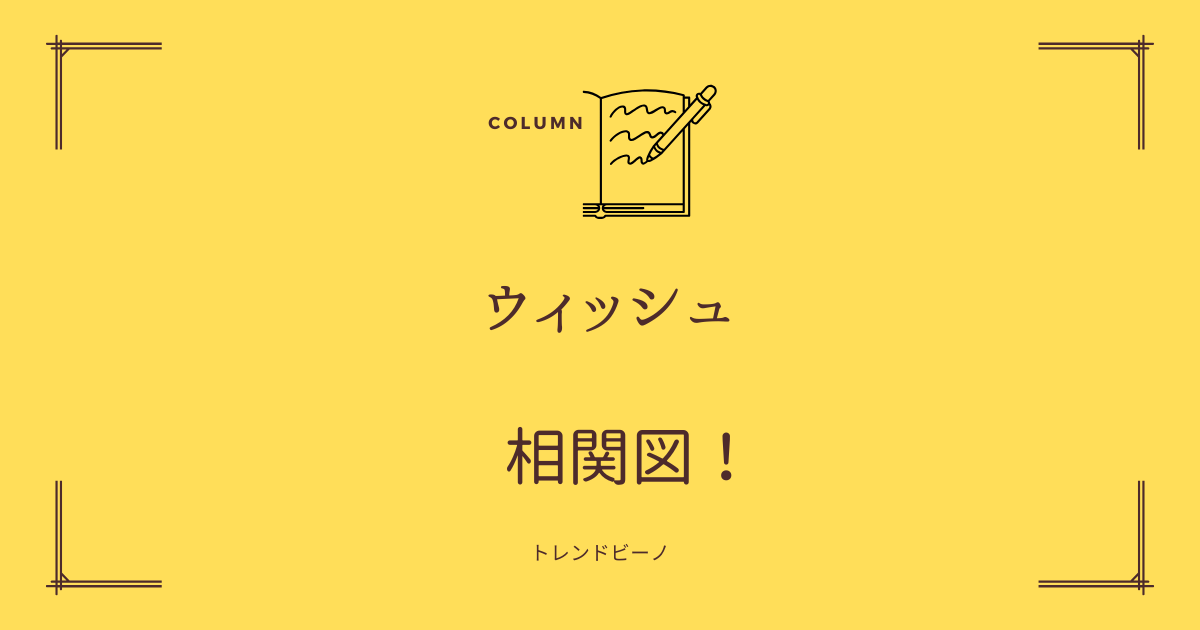
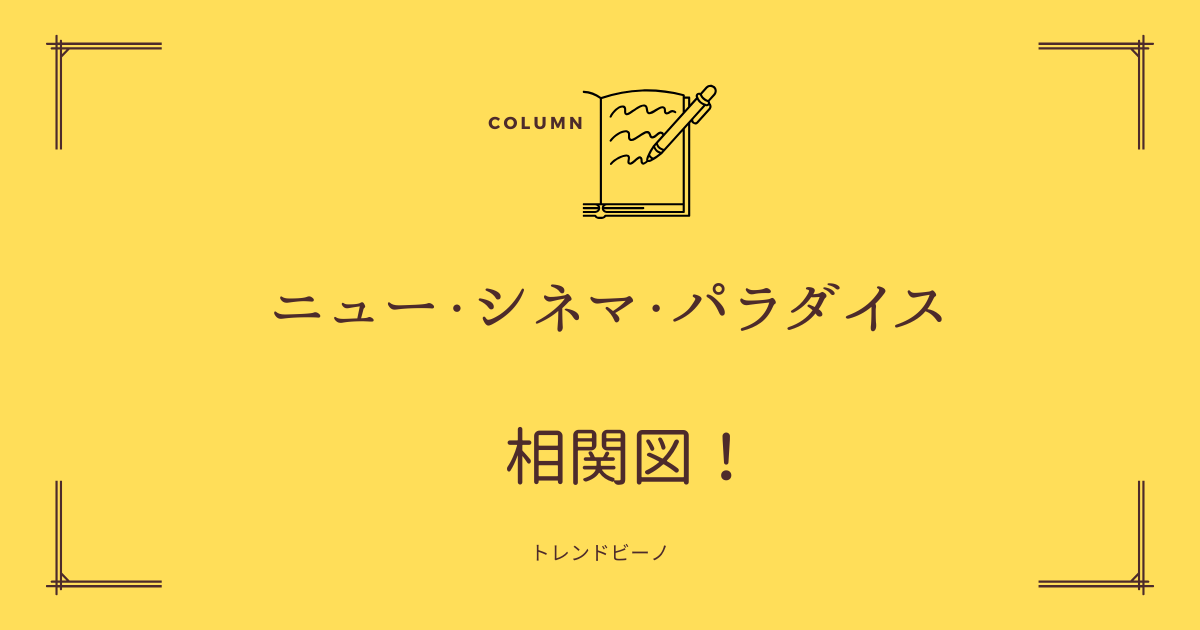
コメント