この映画、いよいよ後半になると「何これ?」ってなる謎モチーフが一気に登場しますよね。黒ずくめの謎の人たちに、天まで届きそうな帆船、そして異様なインコ帝国…。はじめて見たとき「ついていけないかも…」と一瞬ひるんだママさんもいたのでは?
でも大丈夫。このあたりのシーンこそ、じっくり見返してみると、作品全体が伝えようとしていた“大切なメッセージ”がギュッと詰まっているんです。
今回は、ちょっと踏み込んで、下の世界に登場したシンボルたちの正体や意味について、一緒にひもといてみましょう!
無数の帆船の正体は?|“ひとりひとりの宇宙”が漂う幻想の海
海に浮かぶ無数の帆船。あのシーン、見た瞬間「わあ…幻想的」ってなるけど、よく考えるとこの船、全部“幻”だって青サギが言ってたんですよね。じゃあ何の幻?誰の幻?
ここで出てくる考えとしては、あれって「ひとりひとりが持つ“心の宇宙”」なんじゃないかってこと。つまり、それぞれの人生、それぞれの世界観。その象徴としての船たちだったのかなと。
キリコが「しまい波が来る。あの後は穏やかになる」と言っていたのも印象的。波=人生の試練。嵐のような感情や葛藤も、最後の“しまい波”を越えれば、あとは穏やかに心の旅を続けられる。そう語っていたように感じました。
そしてその帆船たちは、誰にも見られないまま消えていく。且つては、それぞれに意味があったそんざいなんでしょうねえ。でも、もしかしたら、ペリカンさんと同じ意味合いで描かれたのかもしれませんね。ペリカンさんは高く高く飛んだ。でも、いつもたどり着いたのはここだった。。みたいな。
帆船も、ほんとは一つながりだった心が、別離を選んだ結果現れた幻だったのかもしれませんね。心って、そういう幻を生み出すとか言われることもありますよね。でも、幻なんだから、それ自体、何かできるわけではない。たくさんに分かれてしまったかに見える、それぞれの心が、何か大志のようなものを抱いて、描き出した幻の数々。それだけに、帆船仕立てで、遠目にも、ちょっと立派な感じで描かれたのかもしれませんね。
下の世界の“幻”として描かれた黒い人や帆船の意味は、こちらの記事で深掘りしています
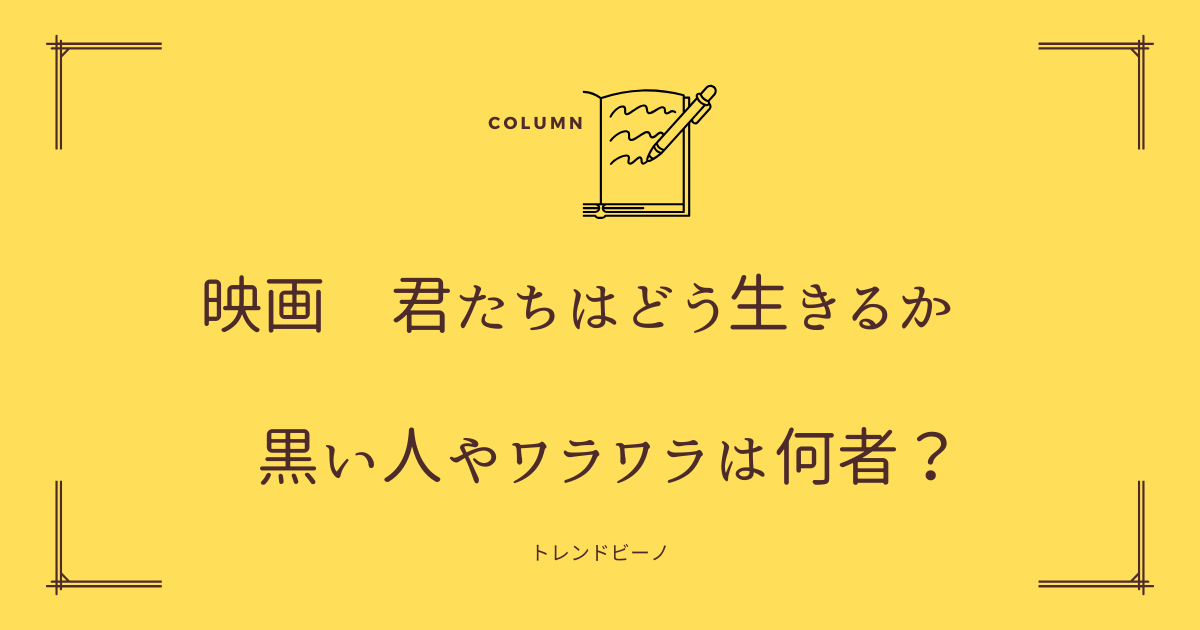
ペリカンの役割とは?|奪い合う“生の本能”を超えていくために
ペリカンって、ちょっと怖かったですよね?「アルケ!食いに行こう!」とか、完全に“食うか食われるか”の世界で生きてる感じ。でも、あの異様なペリカンたち、“学びのない存在”を象徴しているのかもなんておもって、なんとなく、自分自身をえぐられているような、なんだか変な緊張感がありました。
私なんぞは、いつもあれ欲しい、これ欲しい、これ食べたいって、ほんとあのシーンのペリカンか!って思ってしまうような日常。
これって、ただ本能に従って奪い合い、勝ち取ったものを自分だけのものにする――それって、自然界の摂理でありながら、人間の社会にも見え隠れする、いや、私自身の日常に普通に存在する感覚ですよね。
1羽のペリカンが傷つき最期を迎えた時、青サギが言ったんです。「ナムアミダブツ、立派なペリカンでしたなあ」って。
いつもおやつおやつと言いながら、むしゃむしゃやっているような私にも、そういう時が訪れたら、青サギみたいにだれかが、ナムアミダブツ。。。立派な。。。とか言うのかなとか考えたら、なんだか少し笑えて来たり。全く立派じゃないんだけどとか。
黒い人とワラワラとは何者?|“飛べなかった魂”と戦争の影
黒い人たちと、空へ飛び立てずにいた“ワラワラ”。これの意味、しばし考えてみていたんですけど、よく見るとすごく大切なシーンなように感じました。
黒い人たちは、「殺生ができない存在」。じゃあワラワラって何?──あれって滋養がないと飛び立てない魂”のように描かれていました。時は戦争の真っただ中だったんですよね。上の世界の話ですけど。
滋養というのはもしかしたら、上の世界の人たちの、満たされた心の状態などから生じるものなのかなと思ったり、或いは、もっと直接的に、当時の食糧やモノが欠乏していた状況を描こうとされたのか。
キリコさんが「腹いっぱい食わせてあげられてよかった」って言ってましたよね?それって、今までは食べさせてあげられなかったってこと。上の世界で戦争が起きているから、下の世界にもその“欠乏”が広がっていたのかも。魚がいない=滋養がない。
ワラワラが“熟さず、飛び立てなかった”背景には、争いや搾取が影響していた可能性があるって考えると…なんだか胸が苦しくなりますよね。でも、彼らが飛び立てたことで、“少しだけ世界が癒やされたのかな”っていうふうにも見えました。
石と積み木の正体は?|“選択”という意志と、眞人がくだした答え
塔の中で大叔父がやっていた積み木の儀式、覚えてますか?白い積み木をペンでつついて、「これで世界は一日大丈夫だよ」って言うんですけど、その所作がなんとも滑稽で、でもどこか切なくて。
これはまさに、意味のないことに毎日を費やす人間の姿を象徴させようとされたのかなと感じたりしました。ペンでつついてバランスを取るだけで、一喜一憂して、疲れ果てて…でも意味があるようなフリをしてる。
そして、その積み木は“石”だった。「それは木ではありません、墓と同じ石です。悪意があります」って眞人が言うセリフ、鳥肌もんでしたよね。
ここで描かれていたのは、“石(意志)”との契約。大叔父は、自分が築いた幻想の世界を眞人に継がせたかった。でも、眞人はそれを見抜いて、積み木を積むこと=幻想に縛られることを拒絶した。
「友達を探します」という眞人の選択。愛ある関係を築いていくという決意こそが、真の“世界を築く”ということだったんじゃないでしょうか。
積み木と石、そして大叔父の世界の構造についてはこちら
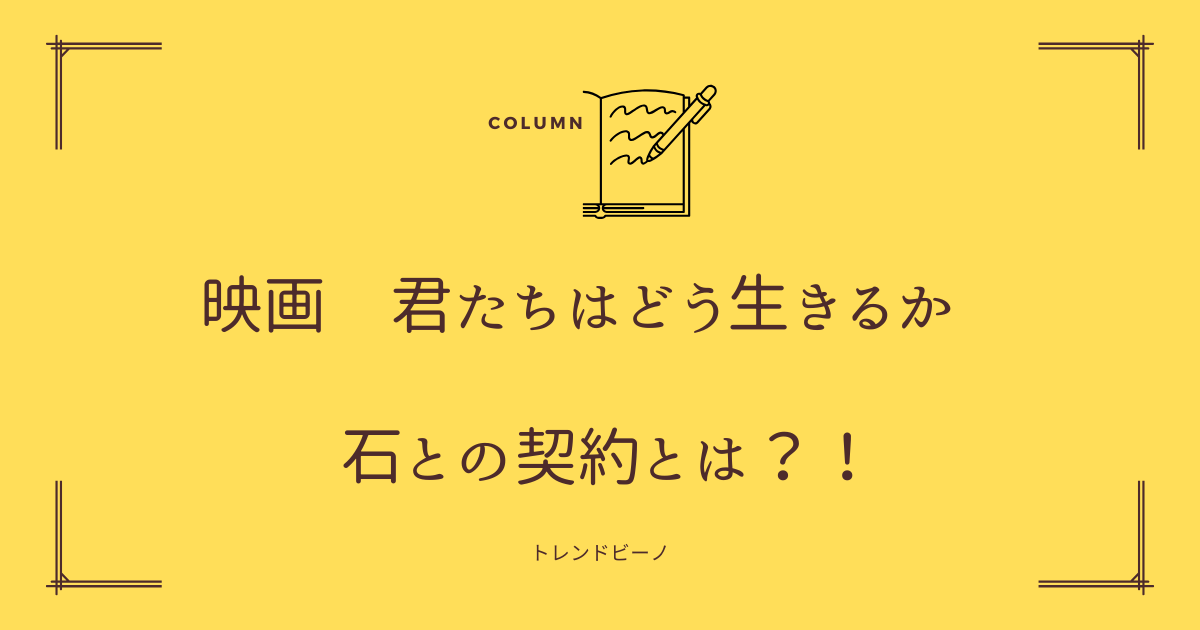
インコ帝国と崩壊の意味|血縁を超えて“愛”を選んだ瞬間
ラスト近くに登場するインコ帝国、あれもまた異質でしたね。「血のつながりがわからぬか!」と怒り叫ぶインコ大王。でもそれって、皮肉ですよね。血のつながりがなければ愛を向けない、って本当は悲しいこと。
この帝国が象徴していたのは、「他者との断絶」、そして「愛の制限」なんじゃないかと。つまり、血のつながりでしか人を大切にできない、というなんともいえない価値観です。
でも眞人は違った。夏子を“母”として受け入れようとし、キリコさんにも、青サギにも、インコにまで愛を向けた。
その瞬間、大叔父の世界=幻想の塔は崩れ始めます。石がざわめき、インコ大王も混乱し…でもそれは決して「悪いこと」ではなくて、“愛の連鎖”が始まった証とかいえるのかも。
大叔父が「戻してやらねばならぬ」と言ったのは、愛に目覚めた眞人を、幻想から現実に解放する“親心”だったのかもとか思ったりします。
まとめ|幻想の塔から抜け出す“鍵”は、ただひとつ「愛」
黒い人も、ペリカンも、帆船も、積み木も、そしてインコ帝国も――全部がこの映画の“心の中の幻想”として描かれていたんじゃないでしょうか。そしてその幻想にどう向き合うかが、眞人の成長を決定づけるテーマだったんだと思います。
眞人が最後に言った「友達を探します」のひとことに、この映画のすべてが込められていた気がしますね。分かち合う、慈しむ、愛を向ける。そこにこそ、幻想から抜け出す鍵がある。
うん、ちょっと難しい内容もあったけど、だからこそ「このシーン、もう一度みてみよ!」って思っちゃいますね。
今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。


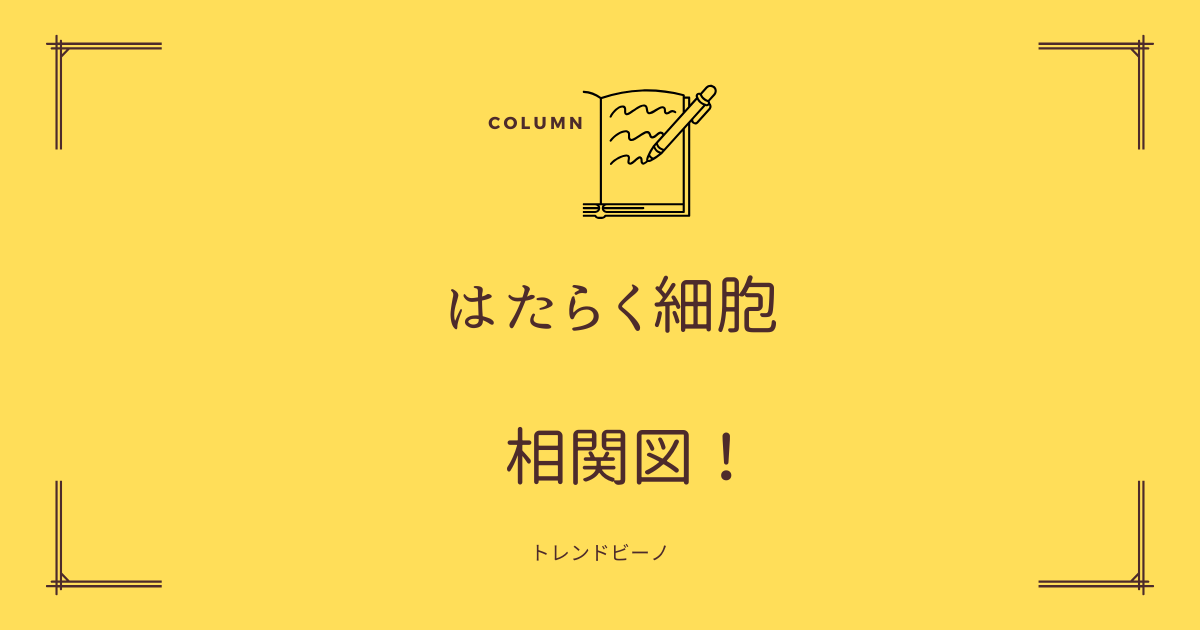
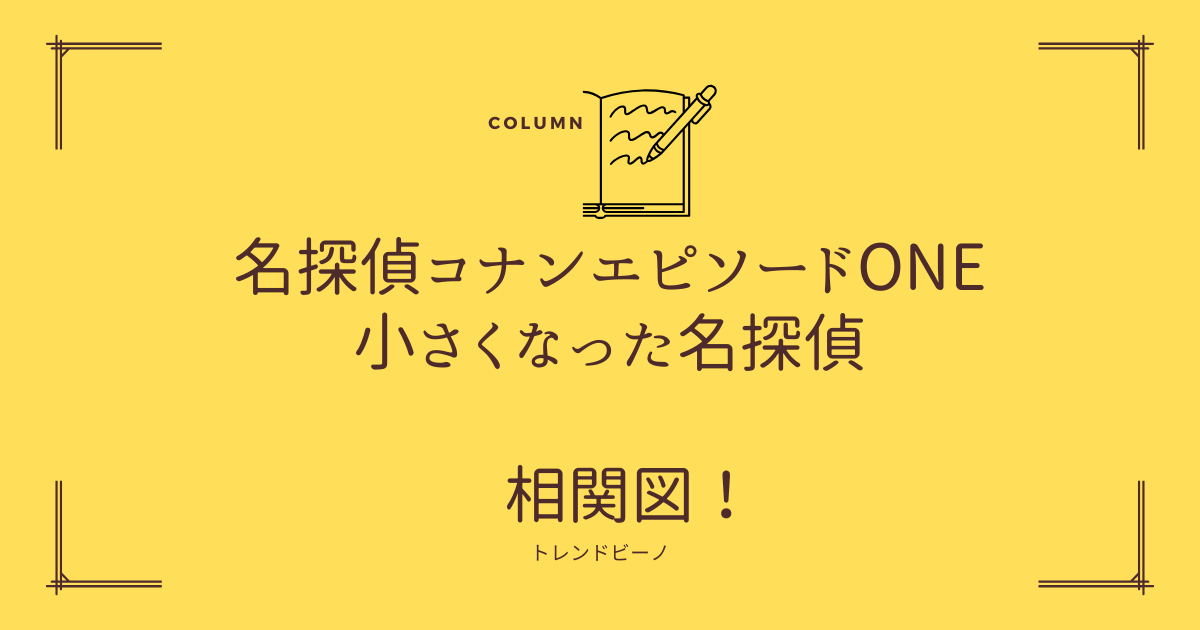

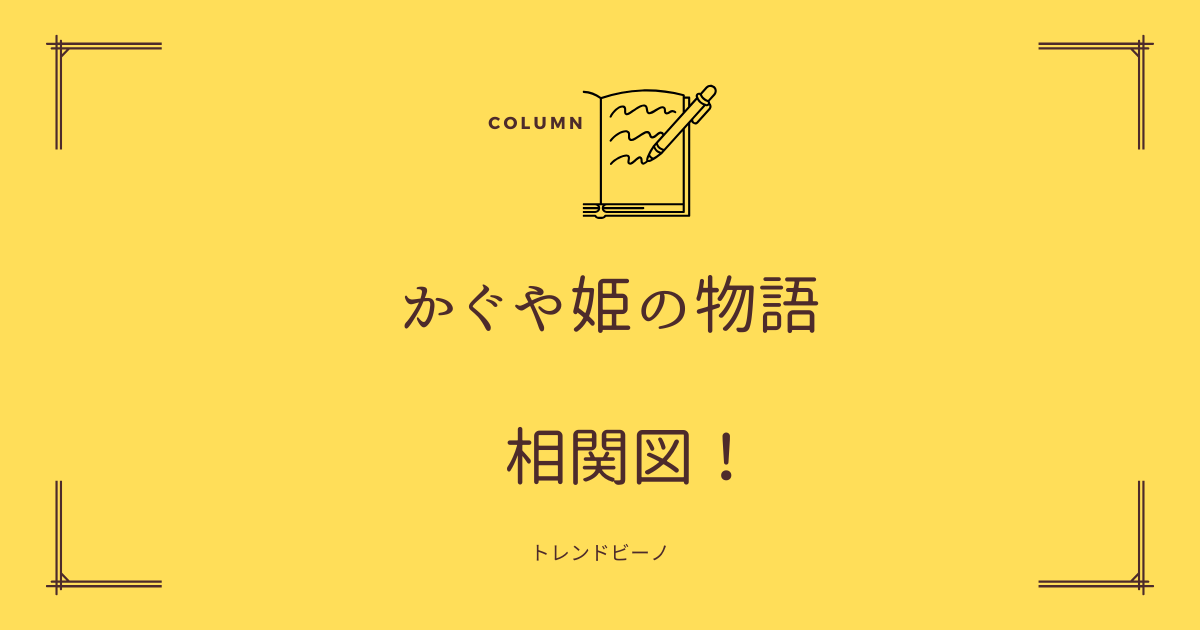
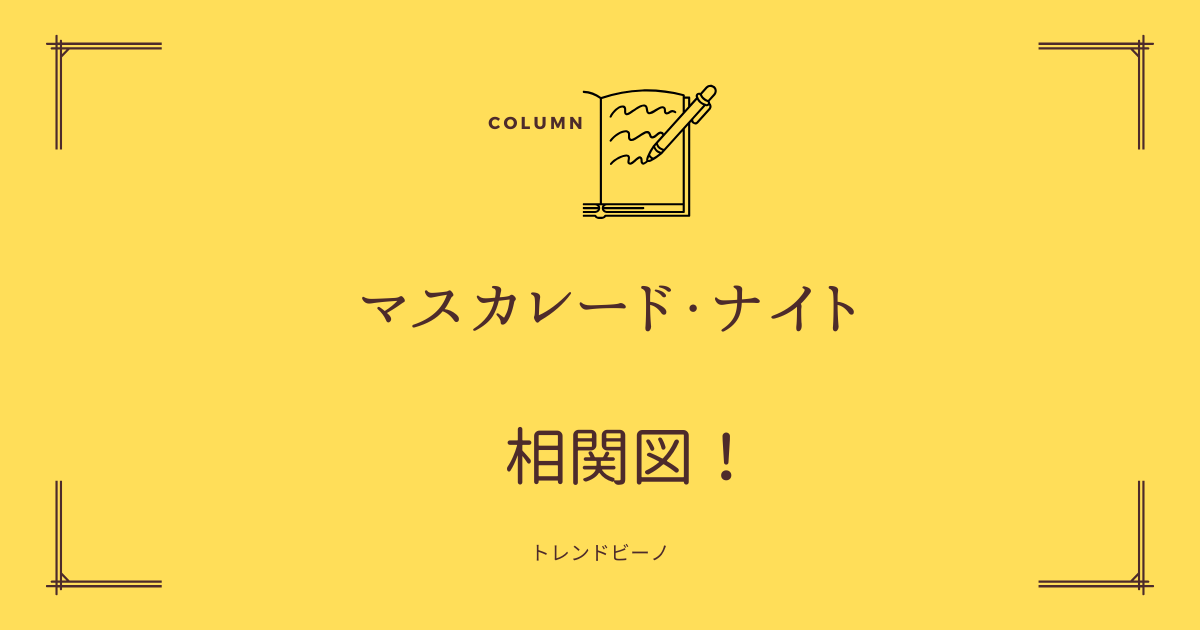
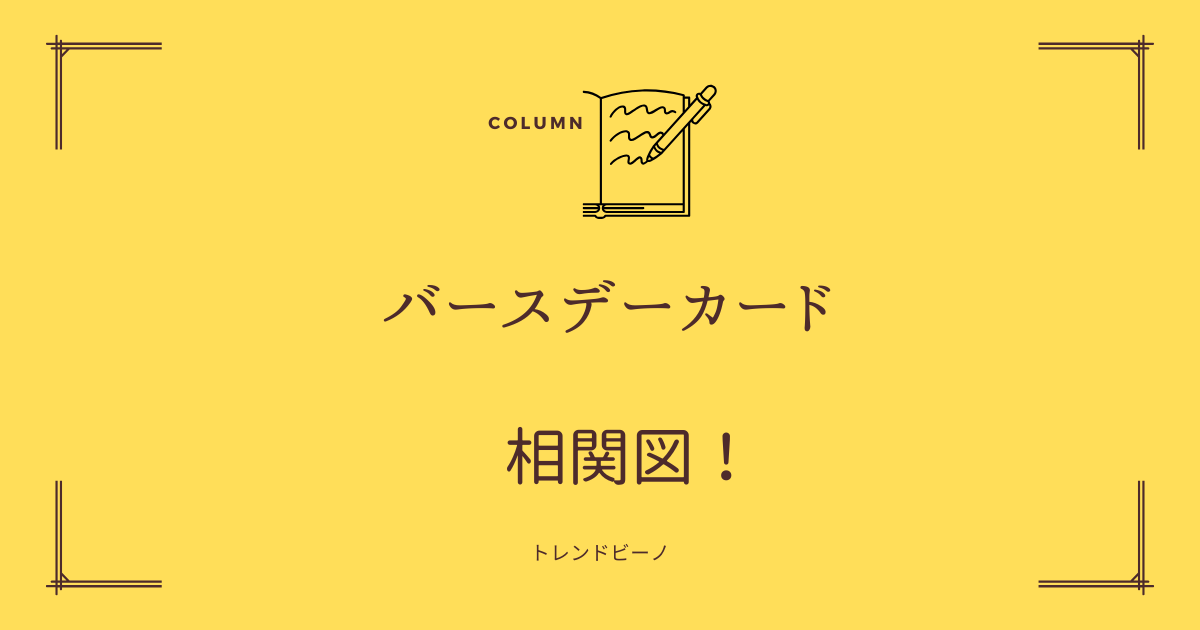
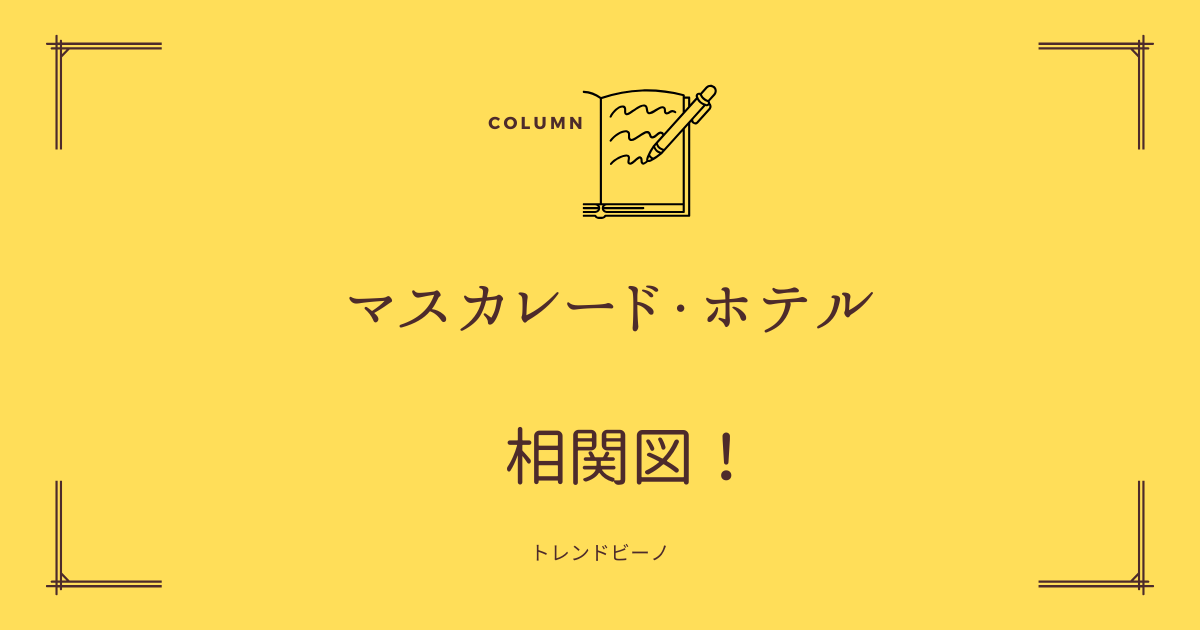
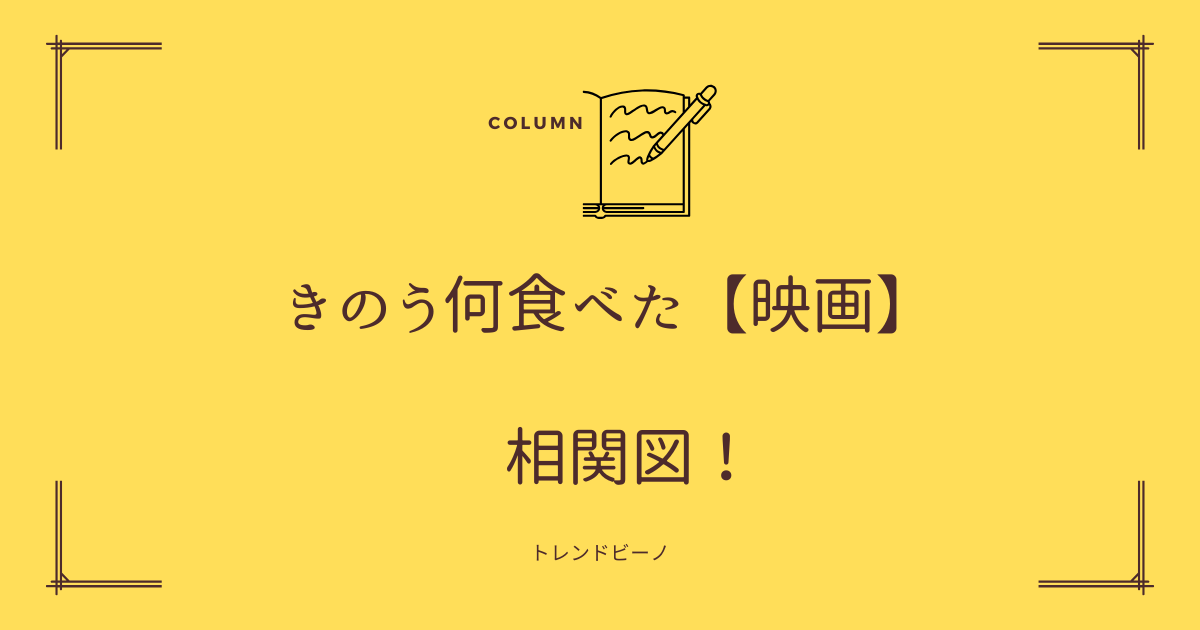
コメント